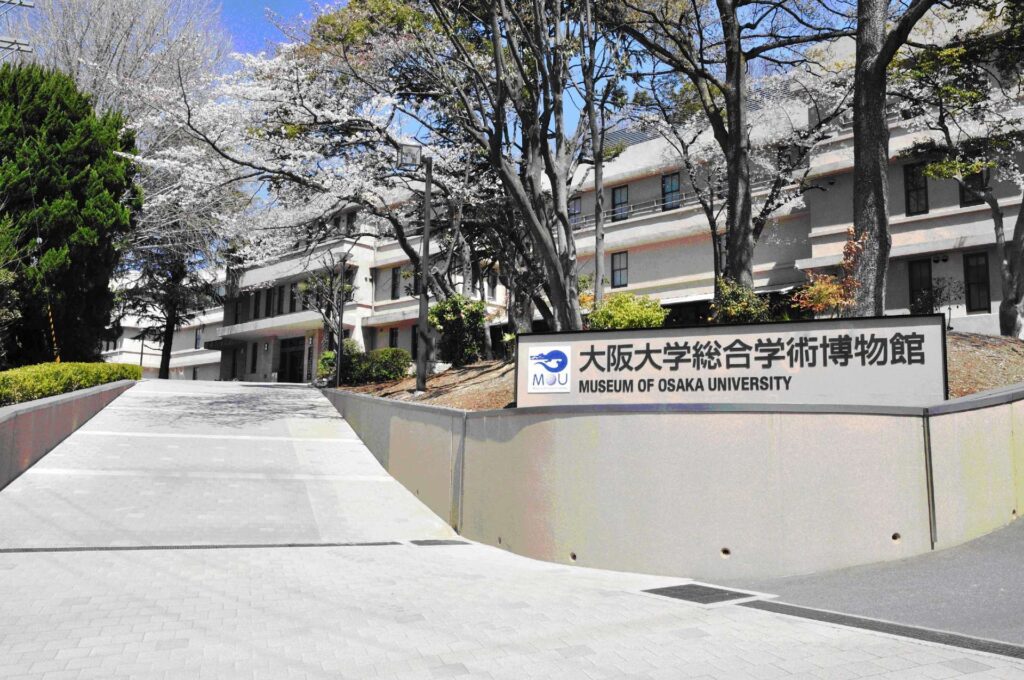
大阪大学総合学術博物館 (The KANSAI Guideより)
A で始まる重要英単語
accumulate [əkjúːmjulèit]
1. 語義解説 (意味) 集める、蓄積する (品詞) 動詞
○ 名詞は accumulation [əkjùːmjuléiʃən]「蓄積」、形容詞は accumulative「蓄積的な」
〇 この単語は 2016年実施東北大学英語入試問題にも出ている。そちらも参照してください。
2. 例文
Although Heck had lived here for four and a half years and had accumulated almost everything that a married then divorced man would by rights accumulate in that time, the rooms were not cluttered.
3. 例文解説
4. 訳例
ヘックはここで 4 年半暮らして、その間に結婚して離婚した男が、当然集めるようなものをほとんど集めていたが、部屋は取り散らかっていなかった。
5. 出典
Jeffrey Deaver, Praying for Sleep (Penguin Books, 1994), p.167.
adjustable [ədʒʌ́stəbl]
1. 語義解説 (意味) 調整できる、順応できる (品詞) 形容詞
○ 動詞は adjust「調節する」、名詞は adjustment「調節」、adjuster は「調整装置」
2. 例文
The bags have adjustable shoulder straps.
3. 例文解説
4. 訳例
それらのかばんには、調節可能な肩ひもがついている。
5. 出典
Collins COBUILD on CD-ROM
agility [ədʒíləti]
1. 語義解説 (意味) 敏捷、機敏さ (品詞) 名詞
○ 形容詞は agile [ǽdʒail]「敏捷な」
2. 例文
She was gasping and panting as she clutched me against her; I was astonished by her strength and agility as she clambered over the rough path, climbing uphill all the while.
3. 例文解説
gasp 「あえぐ、熱望する」
pant 「息切れする、渇望する」
clamber 「よじ登る」
4. 訳文
私をしっかり抱きしめているとき、彼女は喘いで息切れしていた。ずっと上り坂をのぼり、険しい道をよじ登るときの、彼女の力や機敏さに驚かされた。
5. 出典
Margaret George, Helen of Troy (Penguin Books, 2006), p.41.
anagram [ǽnəgræ̀m]
1. 語義解説 (意味) つづり換え、アナグラム (品詞) 名詞
○ アナグラムとは「言葉の綴りの順番を変えて別の語や文を作る遊び」 新村出『広辞苑第六版』(岩波書店、2014年)を参照
2. 例文
What we certainly know to have been done by him in this way, was the Debates in both houses of Parliament, under the name of ‘The Senate of Lilliput,’ sometimes with feigned denominations of the several speakers, sometimes with denominations formed of the letters of their real names, in the manner of what is called anagram, so that they might easily be decyphered.
3. 例文解説
him=Samuel Johnson (1709-84) イギリスの辞書編纂家であり詩人、一般的には Dr. Johnson と呼ばれていた、エリザベス朝の劇作家 Ben Jonson とは綴りが違うので注意
feigned [feind] 「にせの、偽りの」
denomination [dinɔ̀minéiʃən] 「名称、名目」
decipher [disáifə] 「解読する、判読する」
4. 訳例
このように彼が行ったと、私たちがはっきりと知っているものに、「リリパット元老院議員」という名前で上院と下院で行った議論があった。時には、数人の話者の偽名を使ってしたこともあったし、また時には、アナグラムと呼ばれる方法で、本当の名前の文字から名前を作ったので、簡単に解読されるような名前で議論をしたこともあった。
5. 出典
James Boswell (1740年-1795年) スコットランドの法律家、Samuel Johnsonの崇拝者であり、伝記作者。Life of Johnson は James Boswell の 1791 年の作品。
anthropometry [æ̀nθrəpɔ́mitri]
1. 語義解説 (意味) 人体測定法 (品詞) 名詞
〇 形容詞はanthropometric [æ̀nθrəpəmétrik]「人体測定法の」
○ Concise Oxford English Dictionary (Twelfth Edition) (Oxford University Press, 2011) は、anthropometry を “the scientific study of the measurements and proportions of the human body” 「人体の計測と寸法を科学的研究」と定義している
2. 例文
In the 20th century, the application of anthropometry to the study of racial types was replaced by more sophisticated techniques for evaluating racial differences. Anthropometry continued to be a valuable technique, however, gaining an important role in paleoanthropology, the study of human origins and evolution through fossil remains.
3. 例文解説
paleoanthropology 「古人類学」、古人類学とは、古代や化石時代の人類の研究のこと
4. 訳例
20 世紀では、人体測定法の人種類型研究への応用は、人種の相違を鑑定するより複雑な技法に取って変わられた。しかしながら、人体測定法は、化石遺物から人類の起源や進化を研究する古人類学において重要な役割を得て、有益な技術であり続けた。
5. 出典
Encyclopaedia Britannica からの引用
artefact [ɑ́ːtifæ̀kt]
1. 語義解説 (意味) 人工物、芸術品、文化遺物 (品詞) 名詞
○ artifact という綴りもある、Concise Oxford English Dictionary (Twelfth Edition) (Oxford University Press, 2011) は、この語を “a product of human art or workmanship” 「人の芸術あるいは技量が作り出したもの」と定義している
〇 この単語は 2018 年実施大阪大学英語入試問題にも出ている
2. 例文
The factor which distinguishes the artefact from the natural object is that it is the product of human labour.
3. 例文解説
factor 「要因、要素」
it the artefact を指す
4. 訳例
自然のものと人工物を区別する要素は、人工物は人間の労力が作り出したものということだ。
5. 出典
The British National Corpus からの引用
arthritic [ɑːθrítik]
1. 語義解説 (意味) 関節炎にかかった (品詞) 形容詞
○ 名詞は arthritis [ɑːθráitis]「関節炎」
2. 例文
Permit me to present him to you. Monsieur Panbek, gentlemen, has placed his remarkable powers at our disposal for scientific investigation, and we all owe him a debt of gratitude. He is now in his forty-seventh year, a man of normal health, of a neuro-arthritic disposition. Some hyper-excitability of his nervous system is indicated, and his reflexes arc exaggerated, but his blood-pressure is normal. The pulse is now at seventy-two, but rises to one hundred under trance conditions.
3. 例文解説
disposition 「素因、素質」
hyper-excitability [iksàitəbíləti] 「異常興奮」
reflex 「反射、反射運動」
trance condition 「トランス状態」、トランス状態とは「催眠状態などに見られる、常態とは異なる精神状態、この状態では通常の意識が失われ、自動的な活動・思考が現れる」新村出『広辞苑第六版』(岩波書店、2014年)を参照
4. 訳例
この方を紹介させてください。紳士の皆様、パンベック氏は、科学調査のために、氏の能力を私たちの自由にさせてくれています。私たち全員は、彼に感謝しています。彼は現在 47 才で、通常の健康状態であり、神経関節炎の素質があります。神経組織の異常興奮が示されていますが、血圧は正常です。現在、脈は 72 ですが、トランス状態では 100 まで上がります。
5. 出典
Conan Doyle (1859年-1930年) 英国の推理小説家。The Land of Mist は 1926年の作品。
B で始まる重要英単語
bifocal [bàifóukəl]
1. 語義解説 (意味) 遠近二重焦点の (品詞) 形容詞
2. 例文
The aphakic eye is unable to change its focus, so bifocal spectacles are required even for those with contact lenses.
3. 例文解説
aphakic eye [əféikik ái] 「無水晶体眼」眼球に水晶体がない状態、白内障の手術や外傷で起こる
4. 訳例
無水晶体眼は、焦点を変えることができないので、コンタクト・レンズをしている人でさえ、遠近二重焦点の眼鏡が必要になります。
5. 出典
The British National Corpus から引用
C で始まる重要英単語
come up with
1. 語義解説 (意味) 思いつく、発見する (品詞) 句動詞
〇 この単語は 2016 年実施東京大学英語入試問題や 2017 年実施九州大学英語入試問題や 2018 年実施東北大学英語入試問題や 2020 年実施九州大学英語入試問題や 2020 年実施北海道大学英語入試問題や 2020 年実施名古屋大学英語入試問題にも出ている
2. 例文
Tom went to secure a means of transportation, but all he could come up with was an old bicycle with a flat tire.
3. 例文説明
4. 訳例
トムは移動手段を確保しに行ったが、見つけ出したのは、タイヤのパンクした古い自転車だけだった。
5. 出典
ジャン・マケーレブ『動詞を使いこなすための英和活用辞典』(朝日出版社、2006年)
E で始まる重要英単語
epoch [épək]
1. 語義解説 (意味) 新時代、重大な事件が起った時代 (品詞) 名詞
○ 竹林滋『新英和大辞典第六版』(研究社、2013年) は、epoch を「歴史や発展の特定の時代(の始まり)」と説明している
2. 例文
Above all, the warfare of Hester’s spirit at that epoch was perpetuated in Pearl. She could recognize her wild, desperate, defiant mood, the flightiness of her temper, and even some of the very cloud-shapes of gloom and despondency that had brooded in her heart. They were now illuminated by the morning radiance of a young child’s disposition, but, later in the day of earthly existence, might be prolific of the storm and whirlwind.
3. 例文説明
perpetuate [pərpétʃuèit] 「永続させる」
flightiness [fláitinəs] 「気まぐれ、軽はずみ」
gloom 「陰うつ、憂うつ」
despondency [dispɔ́ndənsi] 「失望」
brood 「悩みなどが覆いかぶさる」
prolific [prəlífik] 「たくさん起こる」
4. 訳例
何よりもまず、その時期のへスターの心の戦いは、パールの中で不滅となった。ヘスターはパールの荒々しく絶望的で挑戦的な気分や、気分の気まぐれさ、心に覆いかぶさるまさに雲の形をした憂鬱や失望さえも認識することができた。今、彼女たちは朝の光のような若い子供の気質で照らされているが、後の人生では、嵐やつむじ風が多くなるかもしれない。
5. 出典
Nathaniel Hawthorne (1804年-1864年) 米国の小説家。The Scarlet Letter は Nathaniel Hawthorne の 1850 年の作品。
F で始まる重要英単語
flexibility [flèksəbíləti]
1. 語義解説 (意味) 柔軟性、適応性 (品詞) 名詞
○ 形容詞は flexible [fléksəbl]「曲げやすい、柔軟な」、flextime は「自由勤務制度」
〇 この単語は 2020 年実施九州大学英語入試問題のも出ている
2. 例文
A few naturalists, endowed with much flexibility of mind, and who have already begun to doubt on the immutability of species, may be influenced by this volume; but I look with confidence to the future, to young and rising naturalists, who will be able to view both sides of the question with impartiality.
3. 例文解説
naturalist 「博物学者」
immutability [ìmjùːtəbíləti] 「不変性」
rising 「発達中の」 、the rising generation は「青年層」
impartiality [impɑ̀ːʃiǽləti] 「偏らないこと、公平」
4. 訳例
多くの精神的柔軟性を持っており、すでに動植物分類上の種の不変性を疑い始めている数人の博物学者は、この本から影響を受けるであろう。しかし、私は自信を持って未来と、若くてこれからの博物学者に期待している。彼らはこの問題の両面を公平に見ることができるであろう。
5. 出典
Charles Darwin (1809年-1882年) 英国の博物学者。On the Origin of Species は Charles Darwin が1859 年に著した On the Origin of Species by Means of Natural Selection (『自然淘汰による種の起源について』) のこと。
H で始まる重要英単語
hominid [hɔ́minid]
1. 語義解説 (意味) ヒト科の (品詞) 形容詞
2. 例文
But the serious question is, are we to associate this jaw with the cranium found close by it? If so, it is certainly not chimpanzee nor close to the Apes, but decidedly hominid. Two other small fragments of crania and a few more teeth have been found in the gravel two miles from Piltdown, which agree with the Piltdown cranium in having superciliary ridges fairly strong for a human skull, but not anything like the great superciliary ridges of Apes.
3. 例文解説
cranium [kréiniəm] 「頭蓋」 複数形は crania
Piltdown 「ピルトダウン人が発見されたとされる地名」、なお竹林滋『新英和大辞典第六版』(研究社、2013年) は、ピルトダウン人を「1912年英国 Sussex 州 Lewes 近くの Piltdown で発見された頭蓋; 洪積世最古の人類と想像され、Eoanthropus dawsoni と命名されたが、1953 年に偽物であることが立証された」と説明している
superciliary [sùːpərsílièri] 「眉毛の」
ridge 「隆起」
anything like 「否定や疑問構文で、全然、少しも」
4. 訳例
しかし重要な問題は、私たちはこの顎と近くで発見された頭蓋と結び付けるべきであろうか?もしそうであるならば、それは確かにチンパンジーのものではなく、類人猿にも似ていなくて、疑いもなくヒト科のものである。他の 2 つの小さな頭蓋の断片と数個の歯は、ピルトダウンから 2 マイル離れた砂礫層で発見されたが、人間の頭蓋骨にしてはかなり頑丈な眉の隆起を持っているので、ピルトダウン人の頭蓋と一致しているが、類人猿の大きな眉の隆起とは似ても似つかない。
5. 出典
H. G. Wells (1866-1946) 英国の小説家・文明批評家。The Outline of History は H. G. Wells の1920年の作品。
I で始まる重要英単語
ill-defined [íldifáind]
1. 語義解説 (意味) はっきりしない、不明確な (品詞) 名詞
○ well-defined「はっきりした、明確な」が同じ英語試験問題に出ている
2. 例文
There was a sense within her—too ill-defined to be made a thought but weighing heavily on her mind—that her whole orb of life, both before and after, was connected with this spot, as with the one point that gave it unity.
3. 例文解説
thought 「推論・瞑想などの結果、心に浮かんでくる考え」竹林滋『新英和大辞典第六版』(研究社、2013年)を参照のこと
weigh on 「人・精神を圧迫する」
orb 「行動の範囲」
4. 訳例
彼女の心にはある感覚があった。あまりにもはっきりしないので、考えにまとまらなかったが、彼女の精神に重くのしかかり、彼女の生活範囲すべてが、統一を与える一点かのように、この地点と結びついていた。
5. 出典
Nathaniel Hawthorne (1804年-1864年) 米国の小説家。The Scarlet Letter は Nathaniel Hawthorne の 1850 年の作品。
impairment [impérmənt]
1. 語義解説 (意味) 損傷、悪化 (品詞) 名詞
○ 動詞は impair「悪くする、減じる」
2. 例文
Interestingly, the impairment is of the ability to form new memories, not the ability to recall stored memories.
3. 例文解説
4. 訳例
面白いことに、記憶の悪化とは、新しい記憶を形成する能力についてであり、貯えられた記憶を呼び戻す能力ではない。
5. 出典
ldoceonline.com.dictionary からの引用
infirmity [infə́ːməti]
1. 語義解説 (意味) 虚弱、疾病 (品詞) 名詞
○ 形容詞は infirm「虚弱な、弱い」
2. 例文
When I saw him stood upright before me, I could not be sure to what extent he was hunched over due to infirmity and what extent due to the habit of accommodating the steeply sloped ceilings of the room.
3. 例文説明
4. 訳例
私の前でまっすぐ父が立ったのを見た時に、どの程度まで病気のために前かがみなっているのか、どの程度まで部屋の急な角度のついた天井に合わせる習慣のためなのか、私には確信が持てなかった。
5. 出典
Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (Faber and Faber Limited, 1996), p.68.
in principle
1. 語義解説 (意味) 原則として、大体において (品詞) 副詞句
2. 例文
In principle, my grounds for believing that the earth existed before there was life on it are of just the same sort as my grounds for believing that you saw a kingfisher when you say you did.
3. 例文解説
4. 訳例
大体において、生命の存在の前に地球が存在していたと信じる私の根拠は、あなたがカワセミを見たと言ったときに、本当に見たと信じるのと、私の根拠とまったく同じようなものである。
5. 出典
Bertrand Russel, Human Knowledge (The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd, 2009), p.44.
in the main
1. 語義解説 (意味) 概して、大部分は (品詞) 副詞句
2. 例文
Among present-day philosophies, we may distinguish three principal types, often combined in varying proportions by a single philosopher, but in essence and tendency distinct. The first of these, which I shall call the classical tradition, descends in the main from Kant and Hegel; it represents the attempt to adapt to present needs the methods and results of the great constructive philosophers from Plato downwards.
3. 例文解説
Kant=Immanuel Kant (1724-1804) ドイツの哲学者で『純粋理性批判』や『実践理性批判』などの著作がある
Hegel=Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ドイツの哲学者で、弁証法を唱えた、『精神現象学』などの著作がある、弁証法とは「意見(定立)と反対意見(反定立)との対立と矛盾を通じて、より高い段階の認識(総合)に至る哲学的方法….」新村出『広辞苑第六版』(岩波書店、2014年)を参照
Plato (428-348 B.C.) 紀元前のギリシャの哲学者
4. 訳例
現在の哲学の中で、私たちは 3 つの主なタイプに分類できる。しばしば 1 人の哲学者には、様々な比率で 3 つのタイプが混ざり合っているが、本質と傾向においては明白である。私が古典的伝統と呼ぶ 3 つのうちの第 1 は、大部分カントとヘーゲルから伝わっているものである。それは現在の必要とされるものに、プラトン以降の偉大な建設的な哲学者たちの方法論と結果を当てはめようとする試みを表現している。
5. 出典
Bertrand Russell (1872-1979) イギリスの数学者・哲学者・論理学者。1950 年にノーベル文学賞を受ける。Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy は Bertrand Russell の 1914 年の作品。
J で始まる重要英単語
jump-start
1. 語義解説 (意味) 押して車のエンジンをかける (品詞) 動詞
○ 同じ形で名詞もある
2. 例文
Congress hopes the tax cut will jump-start the economy.
3. 例文解説
4. 訳例
国会は、税金削減が経済のエンジンをかけてくれることを願っている。
5. 出典
ldoceonline.com.dictionary からの引用
L で始まる重要英単語
leave out
1. 語義解説 (意味) 除く、閉め出す (品詞) 句動詞
2. 例文
Give her another hundred years, I concluded, reading the last chapter―people’s noses and bare shoulders showed naked against a starry sky, for someone had twitched the curtain in the drawing-room―give her a room of her own and five hundred a year, let her speak her mind and leave out half that she now puts in, and she will write a better book one of these days.
3. 例文解説
twitch 「ぐいと引く」
leave out 「文字などを省く」
命令+and 「~しなさい、そうすれば」普通、後の文には will を含む
4. 訳例
「誰かが居間のカーテンをぐいと引いたので、人々の鼻とむき出しの肩が、星空を背景にありのままに見えた」という最終章を読みながら、作者の彼女にもう 100 年あげようと、私は結論づけました。彼女に自分だけの部屋と毎年 500 ポンドあげて、彼女の心の内を語らせて、彼女が今書いていることの半分を除外させよう。そうすれば彼女はいつかもっと立派な本を書くでしょう。
5. 出典
Virginia Woolf (1882年-1941年) 英国の女流小説家・批評家。A Room of One’s Own は Virginia Woolf の 1929 年の作品。
M で始まる重要英単語
migrate [maigréit]
1. 語義解説 (意味) 移動する、移住する (品詞) 動詞
○ 名詞は migration [maigréiʃən]「人の移住、鳥などの移動」、同じ名詞の migrant は「移住者、渡り鳥」
2. 例文
I know not whether the day was fair or foul; in descending the drive, I gazed neither on sky nor earth: my heart was with my eyes; and both seemed migrated into Mr. Rochester’s frame. I wanted to see the invisible thing on which, as we went along, he appeared to fasten a glance fierce and fell.
3. 例文解説
in ~ing 「~するとき」
drive 「屋敷内の車道、車回し」
frame 「人体、身体」
fierce 「激しい、強烈な」
fell 「残忍な、すさまじい」
4. 訳例
その日が晴れていたか悪天候だったのか、私は知らない。屋敷内の車道を降りていくとき、私は空も土も見なかった。私の心は目と共にあり、両者ともロチェスター氏の身体の中に移動していた。私たちが進んで行くとき、彼が激しく残忍に睨んでいたように見えた目に、見えないものを、私は見たいと望んだ。
5. 出典
Charlotte Brontë (1816年-1855年) 英国の小説家・詩人。Jane Eyre は Charlotte Brontë の1847年の作品。
N で始まる重要英単語
nectar [néktər]
1. 語義解説 (意味) 花の蜜 (品詞) 名詞
○ 形容詞は nectarous [néktərəs]「甘美な」
2. 例文
I loved the city intensely for its movement of men and women, the soft, fascinating flow of the limbs of men and women, and the sudden flash of eyes and lips as they pass. Among all the faces of the street my attention roved like a bee which clambers drunkenly among blue flowers. I became intoxicated with the strange nectar which I sipped out of the eyes of the passers-by.
3. 例文解説
rove 「目があちこちと動く、きょろきょろする」
clamber 「よじ登る」
intoxicated [intɔ́ksikèitəd] 「酔った」
sip 「すする、吸う」
4. 訳例
男たちや女たちの動き、彼らの柔らかくて魅力的な手足の流れ、彼らが通り過ぎるときの目と唇の突然のきらめきのために、私はその町を激しく愛していた。通りのすべて顔の間を、酔っ払って青い花の中をよじ登るハチのように、私の注意はきょろきょろと動いた。通りがかりの人たちの目から逃れてすすった不思議な蜜で、私は酔った。
5. 出典
D. H. Lawrence (1885年-1930年) 英国の小説家・詩人。The White Peacock は D. H. Lawrence の1911 年の作品。
next to
1. 語義解説 (意味) ほとんど (品詞) 形容詞+前置詞
2. 例文
What vain weathercocks we are! I, who had determined to hold myself independent of all social intercourse, and thanked my stars that, at length, I had lighted on a spot where it was next to impracticable—I, weak wretch, after maintaining till dusk a struggle with low spirits and solitude, was finally compelled to strike my colours; and under pretence of gaining information concerning the necessities of my establishment, I desired Mrs. Dean, when she brought in supper, to sit down while I ate it; hoping sincerely she would prove a regular gossip, and either rouse me to animation or lull me to sleep by her talk.
3. 例文解説
Weathercock [wéðəkɔ̀k] 「風見鶏、心の変わりやすい人」
impracticable [imprǽktikəbəl] 「実行不可能な」
strike one’s colours 「降伏の印として旗を降ろす」
establishment 「住居、世帯」
regular 「まぎれのない」
gossip 「うわさ話の好きな人」
4. 訳例
私たちはなんと下らない風見鶏のように心が変わりやすいのだろうか!すべての社交生活から離れようと決意した私が、終にほとんど社交生活が実行不可能な地点に着地して、運命に感謝していた私が、その惨めな私が、たそがれまでは弱々しく孤独に戦ったあとに、とうとう降伏するはめになったのだ。世帯の必要品に関する情報を得るという言い訳をして、ディーン夫人が食事を運んで来たときに、食事中に側に座っていてほしいと頼んだ。彼女が紛れのない噂好きの人とはっきり示し、私を愉快な気持ちにさせてくれるか、彼女のおしゃべりで私を眠らせてくれることを真剣に望んだ。
5. 出典
Emilie Brontë (1818年-1848年) 英国の小説家・詩人。Wuthering Heights は Emilie Brontë の 1847年の作品。
novel [nɔ́vəl]
1. 語義解説 (意味) 新しい、普通でない (品詞) 形容詞
○ novel「小説」と同じ語源
〇 この単語は 2018 年実施東京大学英語入試問題や 2021 年実施東京大学英語入試問題にも出ている
2. 例文
Clutched in her little fist was the unclean stump of bread she had held for hours. Dicky plucked a soft piece and essayed to feed her with it, but the dry little mouth rejected the morsel, and the head turned feverishly from side to side to the sound of that novel cry.
3. 例文解説
stump 「主要な部分を除いた後の基底部、残片」小西友七『ランダムハウス英和大辞典第二版』(小学館、1987年) を参照
essay 文語で「試みる」
morsel 「少量、小片」
4. 訳例
彼女の小さな拳に握られていたのは、何時間も握りしめていた汚いパンの切れ端だった。ディッキーは柔らかくなったパンを引き抜いて、彼女に食べさせようとした。しかし乾いた小さな口は少しのパンも食べようとせず、奇抜な叫び声に合わせて、首を激しく左右に振っていた。
5. 出典
Arthur Morrison (1863年-1945年) 英国の推理作家。A Child of the Jago は Arthur Morrison の1896年の作品。
P で始まる重要英単語
participant [pɑːtísəpənt]
1. 語義解説 (意味) 参加者、関係者 (品詞) 名詞
○ 動詞は participate「参加する」、名詞は participation「参加」
2. 例文
Participants in the experiment also keep track of what they eat and drink over three days so their eating habits can be evaluated.
3. 例文解説
4. 訳例
その実験の参加者たちは、彼らの食生活が評価できるように、この 3 日間に何を食べたかや何を飲んだかを記録している。
5. 出典
dictionary.cambridge.org からの引用
percentile [pərséntail]
1. 語義解説 (意味) 百分位数、パーセンタイル値 (品詞) 名詞
○パーセンタイルとは、データを大きさの順で並べ百等分し、その順位を見るもの、例文にある九十パーセンタイルは、90/100の点にあるデータ、より詳しくは「企業年金連合会」の HP を参照のこと
2. 例文
The normal upper limits of oesophageal acid and alkaline exposure as defined by the 90 percentile in our normal volunteers was 5.1% and 8.4% respectively.
3. 例文解説
oesophageal [iːsɔ̀fədʒíːəl] 「食道の」
4. 訳例
通常のボランティアの内、90 パーセンタイル値のデータで規定されている食道の酸とアルカリの露出の通常の上限は、それぞれ5.1パーセント (酸) と8.4パーセント (アルカリ) であった。
5. 出典
The British National Corpus からの引用
predate [priːdéit]
1. 語義解説 (意味) 時間的に前にくる (品詞) 動詞
○ 対義語は postdate [poustdéit]
2. 例文
A strong concern about physical appearance seems to predate the development of anorexia nervosa.
3. 例文解説
anorexia nervosa [æ`nəréksiə nərvóusə]「神経性無食欲症」
4. 訳例
身体の容姿への強い関心が、神経性無食欲症の進行より時間的に前に起こるように思える。
5. 出典
The British National Corpus からの引用
prior
1. 語義解説 (意味) 前の、先の (品詞) 形容詞
○ 慣用句の prior to ~ は「~より前に、優先して」
2. 例文
We have already noted that plasticity is the capacity to retain and carry over from prior experience factors which modify subsequent activities. This signifies the capacity to acquire habits or develop definite dispositions. We have now to consider the salient features of habits. In the first place, a habit is a form of executive skill, of efficiency in doing. A habit means an ability to use natural conditions as means to ends. It is an active control of the environment through control of the organs of action. We are perhaps apt to emphasize the control of the body at the expense of control of the environment.
3. 例文解説
plasticity 「適応性、柔軟性」
salient 「顕著な、めざましい」
4. 訳例
適応性とは、今後の行動を修正する以前の経験からの要素を保持し持ち越す能力であることに、私たちはすでに注目した。習慣を獲得するか、あるいは確かな気質を発達させることを、これは意味する。今、私たちは習慣の顕著な特徴を考えなければならない。第一に、習慣は実行する技術の一形態であり、行為の効率化の一形態でもある。習慣は目的を達成する手段として、自然環境を利用する能力を意味する。習慣は行為の器官をコントロールすることによって、環境を積極的にコントロールすることである。私たちはたぶん、環境のコントロールを犠牲にして、肉体のコントロールを強調しがちである。
5. 出典
John Dewey (1859-1952) 米国の哲学者・教育学者。Democracy and Education は John Dewey の 1916 年の作品。
S で始まる重要英単語
settle upon
1. 語義解説 (意味) 決める、決定する (品詞) 句動詞
2. 例文
The persons to whom the children are entrusted should receive the full support and confidence of the parents, otherwise “education lacks its very soul and vitality.” He suggested that a lady of rank should be placed at the head of the nursery, as being better able to understand the responsibilities and duties attached to the education and upbringing of the Queen’s children. His advice was again taken when it was necessary to settle upon what plan the young Prince of Wales should be educated.
3. 例文解説
entrust 「任せる、委託する」
4. 訳例
子供を任される人は両親の完全なサポートと信頼を受けるべきである。そうしないと、「教育はまさに魂と活力を欠くことになる」。女王の子供たちの教育と養育に結びついている責任と義務をより良く理解することができるように、養育の長には身分のある夫人を置くべきだと、彼は提案していた。若いウェールズ王子の教育プランを決定することが必要になったときに、彼のアドバイスがまた取り上げられた。
5. 出典
E. Gordon Browne (1871年-1926年)。Queen Victoria は E. Gordon Browne の 1915 年の作品。
smirk [sməːrk]
1. 語義解説 (意味) にやにや笑う、作り笑いをする (品詞) 動詞
○ 竹林滋『新英和大辞典第六版』(研究社、2013年) は、smirk を「自己満足の、または優越感にひたったにやにや笑い」と説明している
2. 例文
John Wilkes came down the steps to offer his arm to Scarlett. As she descended from the carriage, she saw Suellen smirk and knew that she must have picked out Frank Kennedy in the crowd. If I couldn’t catch a better beau than that old maid in britches! she thought contemptuously, as she stepped to the ground and smiled her thanks to John Wilkes.
3. 例文解説
pick out 「見分ける、見てとる」
beau 「しゃれ男」
britches = breeches 「ひざ丈まであるズボン、半ズボン」
4. 訳例
ジョン・ウィルクスは階段を降りて、スカーレットに腕を差し出した。スカーレットが馬車から降りるとき、スエレンがにやにや笑っているのを見て、スエレンが群集の中でフランク・ケネディを見つけたことを知った。地に足を付けてジョン・ウィルクスにお礼に微笑みかけたときに、「ブリーチを穿いた年増の独身女性のようなフランク・ケネディよりも、しゃれた男を私が掴まえられないなんてあり得ない!」と、彼女は蔑むように思った。
5. 出典
Margaret Mitchell (1900年-1949年) 米国の女流小説家。Gone with the Wind は Margaret Mitchell の 1936 年の作品。
stigma [stígmə]
1. 語義解説 (意味) 汚名、欠点 (品詞) 名詞
○ 動詞は stigmatize [stígmətàiz]「汚名を着せる」
2. 例文
His mind was made up that he was not going to spend all of his days, like James and Andrew, in bargaining, or all his nights, by candlelight, over long columns of figures. He felt keenly, as his brothers did not, the social stigma attached to those “in trade.” Gerald wanted to be a planter.
3. 例文解説
bargaining 「取引、交渉」
those in trade 「商いに関わっている人々」
planter 「農園主」
4. 訳例
ジェイムズやアンドリューのように、商売をして毎日を過ごし、ろうそくの側で、長い数字の列を眺めて毎夜を送ることはしない、と彼は決意していた。彼の兄弟は気づいていなかったが、商いに関わっている人々の欠点を、彼は鋭敏に感じていた。ジェラルドは農園主になりたかった。
5. 出典
Margaret Mitchell (1900年-1949年) 米国の女流小説家。Gone with the Wind は Margaret Mitchell の 1936 年の作品。
strategy [strǽtədʒi]
1. 語義解説 (意味) 戦略 (品詞) 名詞
○ strategy は全体の作戦、tactics は個々の戦闘作戦
〇 この単語は 2016 年実施九州大学英語入試問題や 2016 年実施大阪大学英語入試問題や 2018 年実施東京大学英語入試問題や 2022 年実施京都大学英語入試問題や 2022 年実施東京大学英語入試問題にも出ている
2. 例文
At Louvain the German strategy was the same. The bombardment was only a pretext for the wholesale expulsion of the inhabitants, which was followed by systematic pillage and incendiarism as soon as the ground was clear.
3. 例文解説
pretext reason や excuse より堅い語
Louvain ベルギー (Belgium) の都市、ベルギーは二度の世界大戦でドイツ軍の侵略を受け苦難を経験したので、戦後は中立政策を捨て、北大西洋条約機構 (NATO) に加盟した
4. 訳例
ルーヴァンでもドイツの戦略は同じであった。爆撃はただ住民を大規模に排除するための口実であった。その後に地上が片付くとすぐに組織的な略奪と放火が続いた。
5. 出典
Arnold Toynbee (1889年-1975年) 英国の文明史家。The German Terror in Belgium は Arnold Toynbee の 1917 年の作品。
