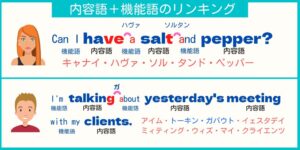『ヘンリー六世』三部作における女性の登場人物について ―家父長制への揺さぶりと再建― (Female Characters in Henry VI Trilogy-The Jolting and Reconstruction of Patriarchy)

ミラ・ジョボビッチ主演「ジャンヌ・ダルク」 リュック・ベッソン監督1999年作品
I シェイクスピア劇に登場する女性たち
『ヘンリー六世』三部作には、それぞれ特徴のある女性たちが登場する。ジャンヌ (Joan Puzel or Pucelle―小田島雄志訳では「乙女ジャンヌ」、松岡和子訳では「乙女」、小津次郎・喜志哲雄訳では「少女ジャンヌ」)、マーガレット (Margaret of Anjou―ヘンリー四世の王妃)、エリナー (Eleanor Cobham―グロスターの妻)、エリザベス(Elizabeth Grey―後のエドワード四世の王妃)である。
歴史劇では王権がテーマとなり、そのために戦争や覇権争いが主な出来事になるので、活躍する登場人物はどうしても男性が中心になるが、ジャンヌとマーガレットは戦争や覇権争いにも参加して男勝りの活躍をする。[注1を参照] マクベス夫人 (Lady Macbeth) は戦争に参加してまで、夫のマクベスを助けようとはしないし、『ハムレット』の世界では、オフィーリア (Ophelia) やガートルード (Gertrude) は非業の死を遂げる受身的な役割しか果たしていない。[注2を参照]
悲劇の登場人物であるマクベス夫人やオフィーリアと比較してみると、歴史劇に登場するジャンヌやマーガレットの特異性が浮かび上がってくるであろう。またエリナーとエリザベスはマイナーな登場人物ながら、歴史劇ならではの役割を果たしている。それは歴史の流れを観客に認識させる働きを持つことである。特にエリザベスは、ヘンリー七世やヘンリー八世の時代との繋がりを考えてみると、重要な働きをしていることがわかる。これらの理由から、悲劇や喜劇とは違った角度から、歴史劇における女性の登場人物を評価する必要があると考えられる。本論文では、歴史劇、特に『ヘンリー六世』三部作における女性登場人物の考察を中心に論を進めることにしたい。
II ジャンヌ・ダルクが象徴する女性性
ジャンヌはフランス軍を助けて、百年戦争を終結させる糸口となるオルレアン解放という目覚ましい働きをする (このため彼女は “the maid of Orleans” と呼ばれる)。歴史上では、彼女はコンピエーニュの戦い (1430年) で捕虜になり、宗教裁判で異端者として有罪となってルーアンで処刑される (1431年)。『ヘンリー六世第一部』の中では、ヨーク (York―第三部でマーガレットから惨殺される) とウォリック (Warwick―キング・メーカー) の尋問によって、処刑が簡単に決まるが (第一部五幕三場)、歴史上では大がかりな異端審問が実施された。このような歴史的事実は別にして、シェイクスピアの劇で明らかなことは、ジャンヌは悪魔の手先として表現されていることである。これは数百年後に書かれたバーナード・ショー (Bernard Shaw) の『聖ジョン』 (Saint John―1923年) のアプローチとはかなり違うが、[注3を参照] シェイクスピアの時代では、ジャンヌは悪魔の手先と一般的には考えられていた。ジャンヌは敵国フランスを窮状から救った英雄であるから、イングランド軍側にとっては、当然な反応であったと考えられる。彼女が聖人と認定されたのは、20 世紀に入った 1920 年のことである。
作品の中でシェイクスピアはジャンヌをどのように描いているのであろうか。詳しく見てみよう。彼女は『ヘンリー六世第一部』五幕三場で、実の父親を真っ向から否定する。「自分は高貴な生まれなので、このような卑しい羊飼いの子ではない」と、次のように言い張るのである。
Decrepit miser, base ignoble wretch,
I am descended of a gentler blood.
Thou art no father, nor no friend of mine. (V.iii.7-9) [注4を参照]
父親を否定する彼女の行為は、当時の観客にかなり悪印象を与えたことであろう。ジャンヌと家父長制との関係は後でも論じるが、彼女の行為は家父長制システムに抵触するものである。その後、「自分は身ごもっているので処刑はできない (I am with child, ye bloody homicides:/ Murder not then the fruit within my womb,/ Although ye hale me to a violent death. V.iii.62-4) とヨークやウォリックに主張して、刑死を逃れようとする。この策略も観客には「潔くない」という印象を与えるであろう。『ヘンリー六世第一部』四幕四場で描かれるトールボット (Talbot) の潔い死の受容とは雲泥の差がある。トールボット親子の悲しい運命の受容とジャンヌの未練たらしい最後は、シェイクスピアがどちらに好意を持っているかを明確にしていると思われる。 [注5を参照] トールボットとジャンヌは、歴史上では同時代に活躍することはあり得ないが、シェイクスピアは彼らを同時代の人物として描くことによって、ジャンヌの悪魔性や政治性を際立たせている。トールボットの最期の台詞は、当時の多くの観客の涙を誘ったことであろう。息子ジョン(John)の死骸を抱いて、最後まで武人としての威厳を失わないトールボットは、ヘンリー六世の宮廷で繰り広げられる政治の汚れた世界あるいはジャンヌが象徴する女性性や悪魔性とは無縁のものである。
Poor boy, he smiles, methinks, as who should say,
‘Had death been French, then death had died today’.
Come, come, and lay him in his father’s arms;
My spirit can no longer bear these harms,
Soldiers, adieu. I have what I would have,
Now my old arms are young John Talbot’s grave. (IV.iv.139-144)
トールボットとは対照的に、ジャンヌの悪魔性の描写は、ウォリックとヨークの尋問前にすでにあった。それは五幕二場で、ジャンヌは悪霊たちに自分を助けることを要求するが、悪霊たちは彼女の要望を聞き届けようとはしない。とうとう彼女は、「じゃあ、私の魂をとりなさい」と魂を売り渡そうとさえする。
Then take my soul—my body, soul, and all—
Before that England give the French the foil. (V.ii.43-44)
上記の台詞から、彼女の守護霊は、歴史上の異端裁判で彼女が主張していた聖カトリーヌ (Catherina de Alexandria) や聖マルグリット (Margaret of Antioch) ではないことが明らかになる (テキストでは、ジャンヌは自分の守護霊を聖母マリアと主張している―I.ii.84-6) 。百年戦争の結果、フランスはヘンリー五世から奪われた領土のほとんどを取り返すが、悪魔に魂を売ったジャンヌの助けを借りたという事実から、悪魔の国という印象をイギリスの観客に与えることになる (テキストではフランス=女性性という図式が頻繁に現れるが、本論文ではフランス=悪魔性を中心に論じることにする)。
シェイクスピアが『ヘンリー六世』三部作を創作している時代は、愛国主義の時代であるから、他国を悪く描くことは許容範囲内であるが、ことさらシェイクスピアがそのように描くのは、当時のスペインとの葛藤が記憶にあるからであろう。スペインの無敵艦隊 (The Invincible Armada) と海戦をして勝ったのは、この劇が作られたほんの 3 年前である (この劇の制作年代を 1591 年と仮定するが、もちろん異説がある)。1588年、スペインのフェリペ二世 (Felipe II) が、フランダースからの陸軍とともに、無敵艦隊をイングランドに送った。その目的はイングランドにローマカトリック教会への信仰を復興させることと、イングランド人による海賊行為を抑制するためであった。イングランドにとって幸いなことに、フランシス・ドレイク (Francis Drake) などの超人的な働きによって辛うじて勝利を得たが、この戦争は他国との力関係が重要であることを、当時の国民の肝に銘じさせたことであろう。[注6を参照] 誤解されやすいことは、この後イングランドが制海権を握ったと勘違いすることである。アルマーダ海戦のあと、スペインは海上を依然として制覇しており、イングランドの脅威となっていたのである。このような時期に『ヘンリー六世』三部作は書かれているという事実はかなり重要なことである。
スペインとアルマーダの海戦を経験したイングランド人観客は、『ヘンリー六世第一部』の舞台上で、ジャンヌという異質の敵と向かい合うことになる。彼らはジャンヌを悪魔の手先と解釈して安心感を得るが (事象が解釈できると安心感が生まれる)、ジャンヌが具現している「悪」は、さらに家父長制システムへの反逆を内包していた。アーデン・シェイクスピアの『ヘンリー六世第一部』の注をしている Edward Burns は、次のような含蓄のある解釈をジャンヌについてしている。
The female sorcerer [Joan Puzel] represents a different idea of historical continuity from that represented by the purposive, forward-moving male warrior or the aged patriarch—she has access to a knowledge of past, present and future, and to a powerful language in which to activate that knowledge, scrambling or reworking the pattern of action in a way that her opponents see as a kind of cheating. [注7を参照]
ジャンヌが象徴する歴史的認識は、男性が体現する家父長制とは相容れないものを含んでいる。そのためトールボットの最期と彼女の最期がまったく異なったものであることは当然の結果であろう。ジャンヌは男性社会に対して、女性的視点を持ち込もうとした異端者 (彼女自身は意識していないが) として位置づけられており、歴史的には、フランス社会からも最後には浮き上がっているので、ジャンヌの女性性はイングランドおよびフランスの家父長制社会から疎んじられたことになる。
III マーガレットとアマゾネス
ジャンヌと同じように、マーガレットも凄まじい一生を送る。彼女は『ヘンリー六世第一部』の五幕二場で、サフォーク (Suffolk) の捕虜となるが、サフォークは彼女をヘンリー六世の妃にしようと考える。彼の計画が明らかになる台詞が次にある。
Yet so my fancy may be satisfied,
And peace established between these realms. (V. ii. 112-113)
上記の台詞から、サフォークがマーガレットを国王の妃にすることは、マーガレットを手元に置いておく手段と同時にイングランドとフランスとの争いの終結という、二股をかける心境であることが分かる。
サフォークの思惑によって、マーガレットはイングランドに王妃として乗り込み、やがてエリナーと対決するようになる。エリナーの夫であるグロスター (Gloucester) は、政治的能力がなく、過去や身分ばかりに拘泥しているから、マーガレット、サフォーク、ウィンチェスター (Winchester) のグループの罠にかかり、エリナーは追放、彼自身は暗殺をされる。政治の世界では非情でなければ、闘争に敗れる運命にあることを、シェイクスピアは明確にしているようである。だがグロスターと妻エリナーを破滅に追いやったマーガレットたちも、大きな歴史の歯車に抵抗できず、彼らもグロスター夫婦と同じような運命を辿る。『ヘンリー六世』三部作の主人公は、登場人物ではなく非情に邁進する非人間的な「歴史」そのものであろう。[注8を参照]
マーガレットがシェイクスピアの描く他の女性と違う点は、前にも記したように、自ら戦争に参加することである。ヘンリー六世はヨークの脅しに負けて、自分が死んだ後はヨークを王にすると誓言したので(第三部一幕一場)、怒ったマーガレットはヨーク追討の兵を挙げて彼を追い詰める。『ヘンリー六世第三部』一幕四場では、彼女は残酷な女性として描かれており、ヨークの息子ラットランド (Rutland) の血を吸ったハンカチで、ヨークの汗を拭かせる所行は、男以上の残酷性を秘めている。一緒にいたノーサンバランド (Northumberland) でさえも、ヨークの姿を見て涙ぐみそうになり、マーガレットから叱責される始末である。
Had he been slaughterman to all my kin,
I should not, for my life, but weep with him,
To see how inly sorrow gripes his soul. (I.iv.169-171) [注9を参照]
さらにマーガレットは『ヘンリー六世第三部』の後半で、ウォリックと組んでフランスから軍隊とともにイングランドに戻り、退位させられていたヘンリー六世を王位に復位させる。このような彼女の男勝りの行為から、彼女がアマゾネスと比較されるのは無理のないことである (“an Amazonian trull” Part 1, I.iv.114) 。言うまでもないことであるが、ギリシャ神話のアマゾネスは家父長制と対立する説話である。
マーガレットは『ヘンリー六世』三部作のあとに位置する『リチャード三世』にも登場して、エドワード四世の寡婦であるエリザベスが、リチャード三世からひどい仕打ちを受けることを予言する。
Poor painted queen, vain flourish of my fortune:
Why strew’st thou sugar on that bottled spider,
Whose deadly web ensnareth thee about?
Fool, fool; thou whet’st a knife to kill thyself.
The day will come that thou shalt wish for me
To help thee curse this poisonous bunch-backed toad. (I.iv.241-6) [注10を参照]
『ヘンリー四世第一部』から『リチャード三世』まで、マーガレットは第一四部作のほとんどに登場する人物であり、シェイクスピアの歴史劇に大きな影を落としている。
ジャンヌはマーガレットのような残酷性は持っておらず、彼女の戦略の一つは仲間割れをイングランド軍に起こすことであった。ジャンヌはイングランドの味方であったバーガンディ (Burgundy) を、イギリス側からフランス側に寝返りをさせることによって、フランス軍の危地を救おうとする。言わば、マーガレットの戦法は正攻法であるが、ジャンヌのやり方は知恵を使った作戦が主となる(これは悪魔性にも関係してくる)。両者とも指揮官として戦争に参加するが、戦争の方法はそれぞれ違う。軍隊を自由に扱えるマーガレットと陣借りをして戦わざるを得ないジャンヌとの違いと言えそうであるが、さらに身分の違いもある。マーガレットは貧乏王の娘とは言え、王位から生まれた身分高い人物であるが、一方ジャンヌは神の啓示を受けたとは言いながら、実質は羊飼いの子供である(彼女自身は否定する)。戦法の違いはどうしようもない。ジャンヌが歴史的に見れば、フランスの主流から浮き上がった存在になったのは、この身分の差も大きな原因であったに違いない。バーガンディ説得の後に、ジャンヌは “Done like a Frenchman; turn and turn again” (III.iv.83) という台詞を吐くが、これはイングランド側の視点からバーガンディの寝返りを見た感想であろう (フランス=女性性というイメージ)。
IV エリナーとウッドヴィル
ジャンヌやマーガレットと比較すると、エリナーとエリザベス・ウッドヴィル (エドワード四世の王妃をエリザベス・ウッドヴィル、彼女の娘をエリザベス・オブ・ヨークと表記する) は、作品中であまり大きな役割を果たすことはない。エリナーは「高慢」が原因で (マーガレットはエリナーを “As that proud dame, the Lord Protector’s wife” Part II, I.iii.77と形容する)、マーガレット一派から罠にはめられるが、その点から言えば、シェイクスピアが描いた他の女性登場人物と変わらない。違うところがあるとすれば、彼女も歴史の大きな歯車の中で翻弄されたという点である。考えてみれば、マーガレットがイギリス国王の妃として乗り込んできた時から、エリナーには勝ち目はなかった。夫のグロスターが政治的な流れを読んで、エリナーを保護・監督しておけば、彼女の事態はかなり好転していたと思われるが、夫の「政治的な詰めの甘さ」が大きな不幸の原因となった。次のグロスターの台詞は、彼の政治的な甘さを露呈している。
Ah, Nell, forbear! Thou aimest all awry.
I must offend before I be attainted.
And had I twenty times so many foes,
And each of them had twenty times their powers,
All these could not procure me any scathe
So long as I am loyal, true and crimeless. (II.iv.58-63)
グロスターの政治的信条は、王に忠誠を尽くし、嘘をつかず、罪を犯さなければ、身を滅ぼすことはない、というものであるが、このような政治的信条はリチャード三世の苛酷な政治手法とは比較にならないほど初心なものである。『ヘンリー六世』という権力闘争の世界では、グロスターはいつか排除されるべき人物であった。
シェイクスピアがエリナーを描いた目的は、彼女もジャンヌと同じように、悪魔と手を結ぼうとしたことにあり、彼女の行為がジャンヌの悪魔性を浮き彫りにする効果を持たせるためである。『ヘンリー六世第一部』で、ジャンヌはすでに処刑されているが、『ヘンリー六世第二部』において、エリナーが悪魔と交渉を持つことによって、ジャンヌの記憶が観客の脳裏によみがえる。さらに悪鬼のようなマーガレット(第二部ではまだ悪鬼までになっていないが)の出自がフランスであることから、悪魔の国=フランスという図式が再度劇中で強調される。
悪魔の国フランスからの軍隊によって、ウォリックとマーガレットはヘンリー六世をもう一度王位に就かせるが(第三部二幕二場)、それがエドワード四世によって覆されるのは、イングランド国民にとっては当然のこととなる。ジャンヌの悪魔性、エリナーの悪魔との交渉、マーガレットのフランス(=悪魔)の出自、これら三つの事象が一緒になって、リチャード三世死後の世界で出現するヘンリー七世の世界を、逆照射するという役割を果たす。逆照射とは、悪魔性が消滅し、正義の行われる政治が実現するという意味である。その時、エリザベス親子は重要な役割を果たす。エリザベス・ウッドヴィルという三部作において最後の重要な役割を果たす女性登場人物は、リチャード三世の暴虐な治世の果てに、ヘンリー七世、ヘンリー八世、エリザベス一世の御代が続くことを暗示する重要な役割を与えられている。ジャンヌやマーガレットが現実世界で活躍することとは反対に、エリザベス・ウッドヴィルは未来の世界を照射する働きを与えられているのである。この点をもう少し詳しく論じてみよう。
オックスフォード・シェイクスピアの『ヘンリー六世第三部』の注釈をしている Randall Martinは、次のように論じて、エリザベス・ウッドヴィルと未来との関係性を否定している。
This story of the country’s fall and recovery was understood by many Elizabethans as God’s plan for his chosen nation, with the Wars of the Roses representing divine punishment being meted out for the original deposition of rightful heir and king, Richard II. But if the play is performed on its own, this wider historical narrative recedes, since apart from Henry’s prophesy in 4.6, Part Three does not support it. Given that Shakespeare did not originally conceive of all these plays as a grand cycle, the play becomes more what it probably was for contemporary spectators: a play about the dangers of political instability, the miseries of civil war, and the compensations of sporadic individual valour. [注11を参照]
シェイクスピアが『ヘンリー六世』三部作構想を最初から持っていたかどうかは定かではない。この疑問はこれからも検討が続けられることであろう。しかしながら、Randall Martinが上記の文章で主張するほど、たとえ『ヘンリー六世第三部』を単独で上演しても(if the play is performed on its own)、ヘンリー六世の予言の衝撃が観客の心に響かないとは考えにくい。ヘンリー六世の予言で、多くの観客はヘンリー七世(とヘンリー八世およびエリザベス一世)の治世を思い浮かべていたと思われる。その予言の衝撃を確信できなければ、シェイクスピアはヘンリー六世にわざわざ劇中で予言を語らせることはないであろう。エリザベスという偉大な女王(エリザベス一世)の名前を持つ登場人物を、シェイクスピアが描いた事実は、彼の壮大な歴史劇の制作意図を感じさせるものとなっている。さらにエリザベス・ウッドヴィルの娘も同名のエリザベスであり、彼女はヘンリー七世の妻となり、紅バラ(ランカスター家)と白バラ(ヨーク家)を結び付ける働きをする。『ヘンリー六世第三部』にあるヘンリー六世の予言の言葉を聞いてみよう。
If secret powers
Suggest but truth to my divining thoughts,
This pretty lad will prove our country’s bliss.
His looks are full of peaceful majesty,
His head by nature framed to wear a crown,
His hand to wield a scepter, and himself
Likely in time to bless a regal throne. (IV.vi.69-74) [注12を参照]
この予言の言葉は、ヘンリー七世、ヘンリー八世を通じて、エドワード四世の妻エリザベス・ウッドヴィルとその娘エリザベス・オブ・ヨークから連なっていくエリザベス一世の治世をも予言しているように思われる。すなわち、エドワード四世と王妃エリザベスの子供であるエリザベス・オブ・ヨークは、エリザベス一世の祖母にあたるので、エリザベス・ウッドヴィル(エドワード四世の妻)→エリザベス・オブ・ヨーク(エドワード四世とエリザベスの娘)→エリザベス一世という血の連続は、バラ戦争で乱れたイングランドを立て直す大きな働きをしているのである。バラ戦争終結のために、エリザベス親子の存在自体が果たす象徴的役割は大きい。またジャンヌやマーガレットから揺さぶりを受けた家父長制も、エリザベス・ウッドヴィルの夫への従順性のため、もとの盤石な地盤を取り戻している。ジャンヌやマーガレットによって、基盤を失いかけた家父長制が、エリザベス・ウッドヴィルという登場人物のために、再び力を取り戻す様子をシェイクスピアは巧妙に描いていると言える。 エドワード四世から求愛の言葉を聞いたエリザベス・ウッドヴィルは、毅然として次のように答える。
And that is more than I will yield unto.
I know I am too mean to be your queen
And yet too good to be your concubine. (III.ii.96-98)
上記の彼女の言葉は、イングランドの家父長制が何らの傷も残さず復活したことを示すものである。夫グロスターとのやり取りから、エリナーも家父長制に揺さぶりをかけているように思えるが、エリザベス・ウッドヴィルはエドワード四世に対して、そのような兆候をまったく見せない。ジェンダー学をシェイクスピア研究に持ち込んだCoppélia Kahnもエリザベス・ウッドヴィルだけには悪魔性を認めていない。[注13を参照] 悪魔性も持たず、家父長制への献身を象徴するエリザベス王妃は、娘のエリザベス・オブ・ヨークとともに、イングランドの未来を示唆する存在であることは間違いない。
注
1) Phyllis Rackin は、ジャンヌとマーガレットを『ヘンリー六世』三部作の中で、 “the best warriors” と評している。
But the Henry VI plays depict the reign of ‘an effeminate prince’ (Henry VI Part One, 1.1.35), where the best warriors are often women. Talbot is unable to defeat Joan in single combat (Henry VI Part One, 1.7), and Queen Margaret is always a better soldier than her husband.
Phyllis Rackin, “English history plays,” in Stanley Wells and Lena Cowen Orlin (eds.), Shakespeare: An Oxford Guide (Oxford U. P., 2003), p. 198.
2) 受身的な役割しか果たしていないからと言って、重要な働きをしていないとは断定できない。例えば、『冬物語』ではハーマイオニー (Hermione) は終始受身的であるが、その従容とした忍耐がレオンティーズ (Leontes) の悔恨を引き出していく。
3) Bernard Shaw の『聖ジョン』については、Jean Chothia, Saint Joan (Methuen Drama, 2008) の Introduction を参考のこと。
4) 『ヘンリー六世第一部』からの引用は、Edward Burns, King Henry VI, Part 1 (The Arden Shakespeare, 2000) からである。なお、『ヘンリー六世第二部』と『ヘンリー六世第三部』の引用は、それぞれ次の版からのものである。Ronald Knowles, King Henry VI, Part 2 (The Arden Shakespeare, 1999) and John D. Cox and Eric Rasmussen, King Henry VI, Part 3 (The Arden Shakespeare, 2001).
5) ジャンヌが火刑で死んだのは 1431 年、トールボットが死んだのは 1453 年である。シェイクスピアは失われつつある「理想の中世騎士像」を創造するために、劇中に登場するトールボットを作り上げ、ジャンヌと対比させたのである。ジャンヌとトールボットとの対照については、次の Jean E. Howard と Phyllis Rackin の説を参照のこと。
…and the gendered opposition between Joan and Talbot defines the meaning of the conflict between France and England. A chivalric hero who fights according to the knightly code, “English Talbot” represents the chivalric ideal that constituted an object of nostalgic longing for Shakespeare’s Elizabethan audience. A youthful peasant whose forces resort to craft, subterfuge, and modern weapons, Joan embodies a demonized and feminine modernity threatening to the traditional patriarchal order.
Jean E. Howard and Phyllis Rackin, Engendering a Nation—A feminist account of Shakespeare’s English histories (Routledge, 1997), p.54.
なお、ジャンヌが発揮する力の曖昧性については、バーガンディの次の台詞が明らかにしている。
Either she hath bewitched me with her words,
Or nature makes me suddenly relent. (III.iii.58-9)
6) 『ヘンリー六世第一部』とスペインとのアルマーダ海戦との関係については、John Cox が論じている。J. D. Cox, Shakespeare and the Dramaturgy of Power (Princeton U. P., 1989) pp. pp. 83-87を参照。
7) Edward Burns, op. cit., p.38.
8) なお、『ヘンリー六世』三部作と『リチャード三世』(第二四部作) の政治的混乱については、「シェイクスピアの第1四部作―政治力学を見据えて―」『英語英文学論叢』第58集、九州大学英語英文学研究会、2008 年、pp.1-10を参照のこと。
9) John D. Cox と Eric Rasmussen もマーガレットについて、次のように述べている。
Moreover, Margaret’s strength may well be a compensation for her husband’s weakness, rather than a cause or symbolic symptom of political chaos.
John D. Cox and Eric Rasmussen, op. cit., pp. 147-148.
ヘンリー六世の精神的弱さを補強して、マーガレットは心身ともに強くならざるを得なかった、というのが彼らの説である。マーガレットとサフォークの深い関係も見逃すべきではないので、次にマーガレットがサフォークの死をあまりにも深く嘆くので、ヘンリー六世がマーガレットに嫌味を言う台詞を引用しておこう。
How now, madam?
Still lamenting and mourning for Suffolk’s death?
I fear me, love, if that I had been dead
Thou wouldest not have mourned so much for me. (IV.iv.20-23)
なお、マーガレットとサフォークの不倫関係は、シェイクスピアの創造である。
Gwyn Williams, “Suffolk and Margaret: A Study of Some Sections of Shakespeare’s Henry VI,” Shakespeare Quarterly Vol.25, No.3 (Folger Shakespeare Library, 1974), pp. 310-322 を参照のこと。
10) 『リチャード三世』からの引用は次の版からのものである。Antony Hammond, King Richard III (The Arden Shakespeare, 1981).
11) Randall Martin, Henry VI, Part Three (Oxford U. P., 2001), p. 51.
12) 『リチャード三世』五幕三場で、ヘンリー六世の亡霊がリッチモンド(Richmond、後のヘンリー七世) を慰めて、次のように語るが、リッチモンドは予言通りボズワース (Battle of Bosworth) の戦いで勝利してヘンリー七世となる。
Virtuous and holy, be thou conqueror:
Harry, that prophesied thou shoudst be King,
Doth comfort thee in thy sleep. Live and flourish! (V.iii.129-131)
13)
In Part 1, as David Bevington has shown, all the female characters―Joan of Aire, the Countess of Auvergne, and Margaret of Anjou―seek mastery over men and all have some access to supernatural power. Men are not depicted as drawn naturally to women; they must be enchanted or hoodwinked into an attachment. (In Part 2, Gloucester’s Duchess Eleanor consorts with witches to gain the throne; only Lady Elizabeth Grey in Part 3 has no associations with the demonic, but nonetheless, Edward’s marriage with her cracks open the Yorkist alliance.)
Coppélia Kahn, Man’s Estate: Masculine Identity in Shakespeare (California U. P., 1981), p. 55.
論文の抄訳
Female Characters in Shakespeare’s Henry VI Plays
―The Shaking and Reconstruction of Patriarchy―
This paper shows that female characters perform a different role in Shakespeare’s Henry VI plays than they do in his comedies and tragedies. Joan Puzel and Margaret of Anjou appear on the battlefield as male characters do in the plays and sometimes defeat male warriors (even Talbot and York). Their action puts pressure on the system of patriarchy in both England and France. Eleanor Cobham and Elizabeth Woodville play a role in the historical context of the trilogy, especially Elizabeth, who symbolizes the future reign of Elizabeth I through the shared name and her support for the patriarchal system of England in her obedience to Edward IV.
Moreover, Henry VI’s prophesy about Richmond, who is later to become Henry VII, also supports her symbolic position in the plays. While Joan and Margaret shake the foundations of the system by defeating males on the battlefield, Elizabeth firmly reestablishes that system through her complete obedience to her husband, Edward IV, leading to the reigns of Henry VII, Henry VIII and Elizabeth I, following Richard III’s defeat by Richmond.