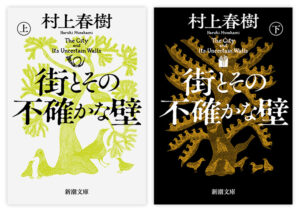村上春樹:職業としての小説家 (Murakami Haruki: a Novelist as an Occupation)
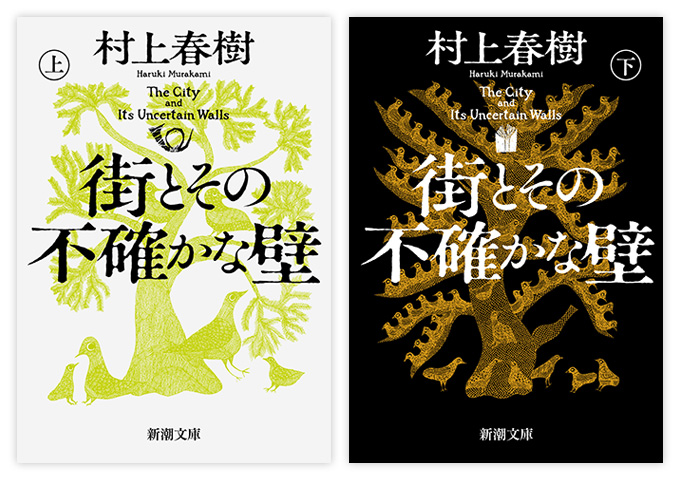
新潮社より村上春樹の『街とその不確かな壁』の文庫本発売の宣伝
村上春樹の『職業としての小説家』(2016年、新潮文庫) の英文版が Novelist as a Vocation: The master storyteller on writing and creativity というタイトルで、2022 年に Knopf 社から発行されることになった。翻訳者は Philip Gabriel と Ted Goossen である。
その一部を The Atlantic (December 2022) という雑誌が取り上げているので、ここに紹介したいと思う。取り上げている英文は、日本文で言えば、第九回「どんな人物を登場させようか」 (Where My Characters Come From) という項目である。
興味深いことは、村上春樹が「作家が登場人物を選ぶのではなく、登場人物が作家を選ぶ」という創作スタンスを取っていることだ。登場人物を最初から想定しているのではなく、話が進んでいくうちに、自然に出てくるのだと、彼は語っている。
確かに、最初から計算づくで物語が進んでいくと、退屈な小説が出来上がるであろう。推理小説などは最初から最後まで、ある程度アウトラインが固まっていなければ、書き進めることはできないであろうが、村上春樹の描く小説世界は、自発的に動く登場人物が活躍することは重要なことであると思われる。
このブログでも、村上春樹の『色彩を持たない田崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋、2013年) の英文を取り上げたが、The Atlantic に掲載された英文に翻訳されたエッセイにも、この作品に言及している部分があるので、その部分に集中して議論を進めてみたいと思う。
小説が順調に進んでいると、物語そのものが前に進んでいく。そしてその典型的な例として、村上春樹は『色彩を持たない田崎つくると、彼の巡礼の年』を取り上げている。
When a novel is on the right track, the characters take on a life of their own, the story moves forward by itself, and the novelist ends up in a very happy situation, just writing down what he sees happening in front of him. And sometimes a character takes the novelist by the hand, leading the way to an unexpected destination.
(訳) 小説が軌道に乗って進んでいるとき、登場人物は自身の生活を送り、物語は自然に前に進んでいく。そして小説家は、自分の前で起こる出来事を、見ているままに書き記すだけという、非常に幸せな状況で終わることもある。時々、一人の登場人物が小説家の手を取り、予期しない方向へと導いていく。
英語に翻訳した Philip Gabriel と Ted Goossen は、「ひとりでに動き出し」という日本文を "take on a life of their own" と訳しており、"spontaneously" とか "automatically" というありふれた単語を使っていない。ここにも彼ら英語翻訳者の日本語能力の卓越さが窺い知れる。"act spontaneously" でも、英語ネイティブには分からないことはないが、少し平板で在りきたりな表現になってしまう。
『色彩を持たない田崎つくると、彼の巡礼の年』という作品は、もともと短い小説で田崎つくるの生活を描写するだけで終わろうと思っていたが、恋人である木元沙羅という登場人物が、田崎つくるに “Not to see what you want to see, but what you must see.” (見たいものを見るのではなく、見なければならないものを見る) と語りかけることによって、新たな展開に入ることになる。そのことを村上春樹は、次のように説明している。
To be honest, until she said that, the idea that Tsukuru needed to go back to see his four friends was the furthest thought from my mind. I’d been planning to write a fairly short story in which Tsukuru lives a quiet, mysterious life, never knowing why he’d been rejected. But once she said that (and I merely wrote down what she said to him), I had to make Tsukuru go to Nagoya and, in the end, send him all the way to Finland. And I needed to then explore those four characters, Tsukuru’s former friends, all over again to show what sort of people they were. And give details of the lives they’d led up to that point.
(訳) 正直に言うと、沙羅がその言葉を言うまでは、つくるが 4 人の友達に会いに行く必要があるという考えは、私の頭にはまったくなかった。なぜ彼が拒絶されたか理由を知らずに、つくるが静かで神秘的な生活を送っているという、極めて短い物語を書こうと計画していた。しかし一旦彼女がその言葉を話すと (私は彼女が彼に言ったことを単に書き記しただけだ)、私はつくるを名古屋に行かせ、最後にははるかフィンランドまで彼を送るはめになった。その上、私はつくるの前の友達であるこれら 4 人の登場人物を調査して、彼らがどのような人物であるかをもう一度示さなければならなかった。またその時点にまで導いた彼らの生活の細部を描く必要があった。
村上春樹の日本語「考えもしませんでした」を、二人の英語翻訳者は "the furthest thought from my mind" と最上級の英単語を使用して表現している。ここも "it is impossible to imagine ~" とか "hardly thinkable" などの表現では、村上春樹の真意は通じないであろう。
ともあれ、上に挙げた例文では、村上春樹は「沙羅が主人公つくるに語る言葉をきっかけにして、短い小説で終わるはずの物語が思わぬ発展に導かれた」と語っている。
上記の作品制作の秘密は、村上春樹の創作技法を少し明らかにしているように思われる (もちろん全てではない)。小説の進行には、作家自身が予測できないことが起きることがあり、それは作家の無意識から起こるのか、あるいは天から啓示が起こすのか、作家自身にも (もちろん読者にも) 分からない。だから、あれほど深い象徴的な小説を、村上春樹は書けるのであろう。