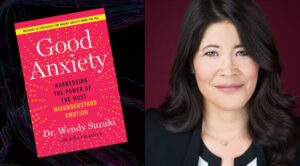脳内血管閉塞ときくち体操 (Vascular Occlusion and Kikuchi Exercise)

済生会福岡総合病院 このブログの作成者は、2018 年から「脳神経内科」の医師にお世話になっている
私の病気の正式名称は「無症候性左中大脳動脈閉塞症」といい、脳梗塞の一種ですが、脳梗塞の症状は出ていない無症状性のものです。このブログで私の病気の詳しい症状と「きくち体操」で克服した経過を記したいと思います。同病の方のご参考になれば幸いです。
(English)
The name of my illness is “asymptomatic left middle cerebral artery occlusion.” It is a type of cerebral infarction, but in my case it is asymptomatic, meaning no stroke symptoms have appeared. In this blog, I would like to describe the detailed condition of my illness and the process through which I overcame it using Kikuchi exercises. I hope this will be helpful to others with the same disease.
1. 発症
今から 7 年前の 2018 年 4 月 20 日の午前と午後に 1 回ずつ、目をつむっていても眩暈を感じた。目の中で景色がぐるぐると回っているようで、気持ちが悪くなり、長く続いたらどうしようかと恐怖を持った。おそらく 10 秒程度で収まったと記憶しているが、眩暈の症状が心配で翌日、近所の耳鼻咽喉科を受診した。耳鼻咽喉科ではメヌエール症候群を疑ったが、検査をしてみても、その症状はなかった。明確な診断がつかないまま、様々な薬をもらい、4 週間くらい飲んでみたが、まったく効果がなかった。耳鼻咽喉科での診察後は、眩暈はしないが、すぐに血圧が上がったり下がったりして、体調はまったくすぐれなかった。包丁を研いでいると、必ず血圧が上昇していたので、不思議に思っていた。それでも病気の内容を知らないので、重い荷物を 2 階から 1 階に運んだりして、今から思えば恐ろしいことをしていた。
(English)
Seven years ago, on April 20, 2018, I experienced dizziness twice—once in the morning and once in the afternoon—even though my eyes were closed. It felt as if the scenery inside my vision was spinning around, which made me nauseous, and I became frightened, wondering what I would do if it continued for a long time. I remember that it subsided after about ten seconds, but I was worried about the dizziness, so I went to a nearby otolaryngology (ENT) clinic the next day. The ENT doctor suspected Ménière’s syndrome, but tests showed that I did not have the condition. Without a clear diagnosis, I was given various medications, which I took for about four weeks, but they had absolutely no effect. After the examination at the ENT clinic, I no longer had dizziness, but my blood pressure would rise and fall rapidly, and I felt generally unwell. Whenever I sharpened a kitchen knife, my blood pressure would always go up, which I found strange. Since I didn’t know the nature of my illness at the time, I even carried heavy items from the second floor down to the first floor—something I now realize was quite dangerous.
2. 診断
2 ヵ月経っても体調が好転しないので、妻が心配して、私の年齢を考えて MRI (磁気共鳴画像) を受診するように強く勧めた。都合の良いことに、車で5 分くらい走ったところに、有名な脳神経外科の医院があった。自分で運転するのは危険なので、その日は娘の車で病院に向かった。それは眩暈を感じて 70 日以上も経過した 7 月 4 日であった。午前中に血液検査等を受けて、午後 MRI を受けることになった。今でも苦手であるが、30 分ほど「ガーン、ガーン」という大音量を聞くことは嫌であったが、病気の原因を探るためには止むを得なかった。翌日には病気の原因が分かり、脳内血管の左側の動脈が閉塞しており、それ以降の血管に血液が送られていなかった。脳梗塞の症状、例えば右手の麻痺 (左脳の障害は身体の右側に現れる)、構音障害 (左脳は言語を司っている) 等が起こらなかったのは、人体の不思議で、血液不足を補うために毛細血管が発達していたからと、医師が説明された。
その翌日の 7 月 6 日に、徳洲会病院で「脳血流 SPECT 検査」を受けた。この検査は、微量の放射能物質を静脈注射して、脳の各部における血流状態や脳の働きを診るものであったが、その画像でも脳内の左側の血液量が不足していることが分かった。徳洲会病院に行った日は大雨で、自宅からの往復にタクシーを使ったが、病気のために陰鬱な気分であった。しかし検査をして下さる看護師さんや検査技師さんの丁重な対応に感動したことを、今でも覚えている。
(English)
Since my condition had not improved even after two months, my wife became worried and strongly urged me—considering my age—to undergo an MRI (magnetic resonance imaging) examination. Fortunately, there was a renowned neurosurgery clinic about a five-minute drive from our home. Because it was dangerous for me to drive myself, my daughter drove me to the hospital that day. It was July 4, more than seventy days after I had first experienced dizziness.
I had blood tests and other examinations in the morning, and an MRI was scheduled for the afternoon. Even now I dislike MRIs, and I didn’t want to endure the loud “gaaan, gaaan” noises for about thirty minutes, but it was unavoidable in order to determine the cause of my illness. The next day, the cause was finally identified: an artery on the left side of my brain was occluded, and blood had not been flowing to the vessels beyond that point.
It was a mystery of the human body that I had not developed any stroke symptoms—such as paralysis of the right hand (damage to the left brain manifests on the right side of the body) or speech impairment (the left brain controls language). The doctor explained that this was because capillaries had developed to compensate for the lack of blood flow
On July 6, the day after that, I underwent a “cerebral blood flow SPECT scan” at Tokushukai Hospital. In this test, a small amount of radioactive tracer is injected intravenously to observe blood flow and brain function in various regions of the brain. The resulting images also showed that the amount of blood in the left side of my brain was insufficient. It was raining heavily on the day I went to Tokushukai Hospital, so I took a taxi to and from my home. Because of my illness, I felt gloomy, but I still remember how moved I was by the courteous care provided by the nurses and technicians who conducted the examination.
3. 病院選び
そのまま近所の脳神経外科のお世話になる選択肢もあったが、セカンド・オピニオンを聞くために、済生会福岡総合病院を受診した。この日は眩暈の発症から 3 ヵ月近く経過した 7 月 18 日であった。近所の脳神経外科の先生は有名な方で、腕もしっかりされているという評判であったが、個人病院なので、先生が留守の折に、私が急に具合が悪くなったときに不安なので、数人の脳神経外科や脳神経内科の先生方が在籍されている済生会福岡総合病院にお世話になることを最終的に決めた。ここであれば、私に何かあったときに、救急車で運ばれてくるだけでよいと考えると安心であった。済生会病院での私の主治医は 、40 代半ばの誠実な先生で、この方にはすべてを任せてもよいと直感で感じた。
(English)
I could have continued receiving treatment at the local neurosurgery clinic, but I sought a second opinion and decided to visit Saiseikai Fukuoka General Hospital. This was on July 18, nearly three months after the onset of my vertigo. The doctor at the local neurosurgery clinic was well known and reputed to be highly skilled, but because it was a private clinic, I felt uneasy about what might happen if I suddenly became ill while the doctor was away. For that reason, I ultimately decided to place myself in the care of Saiseikai Fukuoka General Hospital, where several neurosurgeons and neurologists are on staff. I felt reassured knowing that if anything happened to me, I could simply be brought there by ambulance. My attending physician at Saiseikai Hospital was a sincere doctor in his mid-forties, and I intuitively felt that I could entrust everything to him.
4. 手術か薬か
この病気には、手術と薬で様子をみる方法があり、近所の脳神経外科や済生会の先生から、どちらかを選択するように言われたが、私は薬で様子を見ることを選んだ。薬を選択する前に、インターネットで私の病気の治療法を検索したが、手術はあまり成績が良くなかった。手術は頭皮の血管を、バイパスで脳内血管につなぐ手法で、脳内血流を増やすものであるが、欧米ではほとんどされてなかった。日本では手術で治癒を見込める患者を選んで実施しているので、ある程度成績が良いとのことであった。
(English)
There were two approaches to treating this illness—surgery or medication—and both the local neurosurgeon and the doctor at Saiseikai advised me to choose one. I opted for medication. Before making that decision, I searched online for treatment methods for my condition, but the outcomes of surgery did not seem very good. The surgery involves connecting a scalp artery to an intracranial artery using a bypass to increase blood flow to the brain, but it was rarely performed in Western countries. In Japan, the procedure was carried out only on patients expected to benefit from it, so the results were said to be reasonably good.
5. その後の養生
この病気で悪いことは肥満であった。このため診断から 1 年間で 10 キロ体重を落とした。ある日、ズボンがすべて大きくなったので、新しいズボンを買いに行ったとき、更衣室で全身を映したとき、これが自分の姿かと疑うほど骨と皮になっていた。妻の努力のおかげで、塩分をなるべく少量にしたり、食事の分量にも最大限に気を配った食事をとることができた。食事に関しては、今でも妻に感謝している。妻がいなければ、おそらく病気は重くなっていたかもしれない。おかげ様で、もうすぐ 7 年が経過しようとしているが、体調は非常に良い。
食事の次は、まず歩くことに専念した。最初は 8000 歩を目標にして、iPhone を持って、散歩に行ったり、書斎でその場足踏みをした。現在はあまり無理をしないように、毎日 6000 歩ほど歩くことにしている。考えてみれば、毎日これほど身体を動かしたことはない。40 年間、大学教員を勤めたが、ほとんど身体を動かすことなく、食欲に任せて大量の食事をしていた。おまけに、アイスクリームなどを研究室の冷蔵庫に入れて置き、気の向いたときには食べていた。このような病気になったのは、当然の結果であった。
(English)
One factor that worsened this illness was obesity. For that reason, I lost 10 kilograms within a year of being diagnosed. One day, when I went to buy new trousers because all my old ones had become too large, I saw my whole body in the fitting-room mirror and was shocked at how thin and gaunt I had become—almost just skin and bones. Thanks to my wife’s efforts, I was able to eat meals with as little salt as possible and with careful attention to portion size. I am still grateful to her for that. Without her, my condition might have become much more serious. Thanks to her support, nearly seven years have now passed, and my health is very good.
After improving my diet, I focused on walking. At first, I set a goal of 8,000 steps a day, carrying my iPhone when I went out for walks, or marching in place in my study. These days, I try not to overexert myself and walk about 6,000 steps daily. Looking back, I realize I had never exercised this much in my life. For forty years I worked as a university professor, barely moving my body and eating large amounts of food as I pleased. To make matters worse, I kept ice cream in the lab refrigerator and ate it whenever I felt like it. Developing this illness was, in a sense, an inevitable result.
6. きくち体操
何といっても、私の体調が良いのは、「きくち体操」のおかげである。体調が最悪の時、梅沢富美男さんのテレビ番組で「きくち体操」を取り上げていた。梅沢さんの義母もこの体操で立ち上がることができるようになったとのことである。「これだ!」と思い、さっそく資料をアマゾンに注文して、きくち体操を試してみた。中学生のころ、柔道をして、初段を持っていたが、それ以降は何の運動をしていなかったので、最初は身体のあちこちがぎしぎし音をたてるようだった。それを我慢して半年間継続すると、ある日、気分が朝から晴れやかな日があった。「私が求めていたものはこれだ!」という感をますます強くした。
それ以降、毎日「きくち体操」を実施している。ただ最近、あまり体調が良いので、ときどき「きくち体操」をさぼることがあり、忸怩たる思いをしていた。そこでこのサイトで「きくち体操」に触れているというメールを、きくち体操の事務局に差し上げたら、思いがけず菊池和子先生から直接メールを頂いた。さっそくお礼にメールを差し上げようとしたが、お忙しい先生にご迷惑ではないかと思い、この場を借りて先生に御礼を申し上げることにした。菊池和子先生、本当にありがとうございました。
(English)
Above all, the reason my health is good now is thanks to Kikuchi Exercises. When my condition was at its worst, a TV program hosted by Tomio Umezawa featured Kikuchi Exercuses. He mentioned that his mother-in-law had also regained the ability to stand up through these exercises. I thought, “This is it!” and immediately ordered the materials from Amazon to try the exercises myself. I had practiced judo in junior high school and held a first-degree black belt, but since then I had done no exercise at all. As a result, when I first started, my body creaked everywhere as if rusty. But after persevering for six months, one morning I woke up feeling unusually refreshed. My conviction grew stronger: “This is exactly what I’ve been looking for!”
Since then, I have practiced Kikuchi Taiso every day. Recently, however, because I’ve been feeling so well, I sometimes skipped the exercises and felt guilty about it. So I sent an email to the Kikuchi Taiso office to tell them that I had written about the exercises on this website. To my surprise, I received a direct reply from Ms. Kazuko Kikuchi herself. I intended to send a thank-you email right away, but I hesitated, worried that it might trouble her since she must be so busy. Therefore, I would like to take this opportunity to express my gratitude to her here. Ms. Kazuko Kikuchi, thank you very much.
7. 近況報告
現在から 数年前の 2021 年 10 月 7 日に、お世話になっている済生会福岡総合病院で、「脳血流 SPECT 検査」を 3 年ぶりに受けた。その結果は驚くべきものであった。脳の左側動脈が閉塞しているので、当然左側の脳内血流が少ないはずであるが、検査の結果、脳の左側の血流が、右側よりも活発であった。この結果には主治医の先生も驚いておられた。これも「きくち体操」のお陰ではないかと思っている。病気が回復しても、それに慢心せずに、これからも毎日「きくち体操」を実践していきたい。
2024 年に MRI を受けたが、脳内の状況は発症当時とほとんど同じであった。主治医の先生は、「薬の効果だけでなく、患者の日常生活も大いに関係があったと思われる」とおっしゃっていただいた。
(English)
On October 7, 2021—several years ago from the present—I underwent a cerebral blood flow SPECT scan at Saiseikai Fukuoka General Hospital, where I have been receiving care. It was my first scan in three years. The results were astonishing. Since the artery on the left side of my brain is occluded, the blood flow on the left side should naturally have been lower. However, the scan showed that the blood flow on the left side was actually more active than on the right. My attending physician was also surprised by this result. I believe this may well be thanks to Kikuchi Taiso. Even though my condition has improved, I do not want to become complacent; I plan to continue practicing Kikuchi Taiso every day.
In 2024, I underwent an MRI, and the condition inside my brain was almost the same as when the symptoms first appeared. My doctor told me, “It seems that not only the effects of the medication but also your daily lifestyle played a major role.”