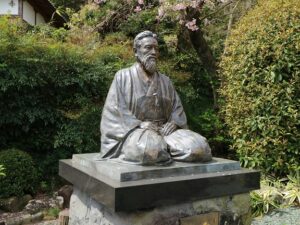文脈学習 (Contextual Learning)

代々木ゼミナール札幌校
日本屈指の予備校
多くの受験生を志望校に入学させている
2023 年大学共通テスト
2023 年実施の大学共通テストが、1 月 14 日と 15 日に無事終了した。受験生の皆さん、お疲れさまでした。今年は昨年のような事件も起こらず、大学で教えた身としては、ほっとするものがあった。
英語の問題に関しては、出題形式や大問数は昨年と同じで、受験生は落ち着いて問題に取り組めたと思います。代々木ゼミナールの講評では、「昨年同様、日常の場面を意識した多様な英文が出題された。英文の総語数は昨年に引き続き約 6000 語と多く、素早く必要な情報を読み取る力が問われている」とあり、なるほどと納得させられた。
大学で英語の教授を 40 年間勤めた経験のあるこのサイトの作成者は、大学共通テストの英文を読んでいて、"contextual learning" という言葉に興味を持った。この用語は、相当以前から提唱されていたようだが、私にはあまり聴き慣れない言葉であった。教育関係の論文や著書には、ざっと目を通していたが、勉強不足は恥ずかしい限りである。おそらく当然の事として考えて、気にも留めてなかったのであろうと思われる。
文脈学習の解釈
ネットでこの単語を検索してみると、Times Higher Education (4 Mar 2022) に "Contextual learning: linking learning to the real world" という記事が見つかった。それによると、"contextual learning" は、次のように要約できる。
The principle of “Contextual learning” explores how bringing learning into context can make the experience more meaningful to students. As part of the process of exploring content across different contexts and seeing how it is relevant, a contextualised learning experience prepares students for life outside the classroom.
(訳) 「文脈学習」の根本方針は、学習を文脈に当てはめることが、学生にとって学習経験をどのようにして意義あるものにできるかを、調査することである。異なった状況で内容を調査して、どのように関連しているかを理解する過程の一環として、文脈学習経験は、教室の外での生活に対して、学生たちを準備させるものである。
少し抽象的な書き方で分かりづらいので、他の文献を見てみよう。"Tools for Contextual Learning" (文脈学習の手段) を標榜している Cord Communications は、学習者は学習内容と実生活がどのように結びついているかを知りたがっている、と考えている。確かに、難しい数学など、日常生活で何の役に立つかを知りたいと思うのは、人間の情であろう。
Many students have a difficult time understanding academic concepts (such as math concepts) as they are commonly taught (that is, using an abstract, lecture method), but they desperately need to understand the concepts as they relate to the workplace and to the larger society in which they will live and work. Traditionally, students have been expected to make these connections on their own, outside the classroom.
(訳) 多くの学生たちは、通常教えられているような (すなわち、抽象的で講義形式を用いて)、 学問的概念 (例えば、数学概念) を理解するのに、苦労しているが、その概念が、彼らが生活し働く職場やより大きな社会と、どのような関連があるかを、彼らは理解することを非常に必要としている。伝統的には、学生たちは、教室外では自分でこの関連を見つけるように期待されていた。
数学は実社会で役に立つか?
数学と実社会を関連付けることは難しいと思われる。三次方程式や関数など、実社会で使用することはほとんどない。数学を学ぶ必要があると、学生に強制することはかなり困難であろう。だが数学の学習で涵養される論理能力は、実社会でも役立つ。また統計の概念は、これからの社会では、必須の能力と言える。まだ頭脳が柔軟な間に、このような難解な科目を学習することは有意義な体験である。
社会で習う概念は、社会人として知っておかなければならないことが多い。この科目は学生が社会に出ていくときに必要なもので、わざわざ役に立つかどうか尋ねることもないと思われる。
英語に関しては、実社会で役に立つことは明らかであるが、それはコミュニケーションの道具としての英語である。難解な英文を読むことなど、実社会ではほとんど機会がないと思われる。
しかし大学に入れば、ある程度英文読解力がないと、専門の研究ができない。英語の論文を読み、英語で発表する必要があるからである。理系の論文では、日本語で書いてもほとんど読まれることはないという話を、大学で働いていた時に聞いたことがある。