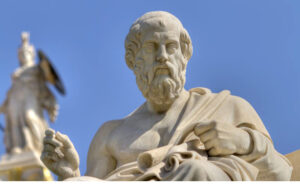民主主義の危機 (The Crisis of Democracy)

日本の民主主義を守る国会議事堂 東京都千代田区永田町 1936 年に完成
民主主義の基礎が危機
2015 年実施の神戸大学の英語入試問題は、民主主義の危機についての英文を取り上げている。危機とは 2008 年に始まった世界的な経済危機ではなく、気づかれにくいが、民主主義の基礎を覆すような危機である。
No, I mean a crisis that goes largely unnoticed, like a cancer; a crisis that is likely to be, in the long run, far more damaging to the future of democratic self-government: a worldwide crisis in education.
(訳) 経済的な危機ではなく、ガンのようにほとんど気付かれなく進行する危機である。長期的に見れば、それは民主主義自治の将来にとって、経済的危機以上に有害なものである。それは教育における世界的な危機である。
筆者が取り上げているのは、教育の危機であり、それは民主主義の将来にとっては痛手となるものである。
Radical changes are occurring in what democratic societies teach the young, and these changes have not been well thought through.
(訳) 根本的な変化が、民主社会が若者に教えることに起きている。そしてこれらの変化は、あまりじっくりと考えられてこなかった。
利益追求の国家
このような重大な変化を、国家が考えなかったのは、利益追求を第一に考えたからである。
Thirsty for national profit, nations, and their systems of education, are heedlessly discarding skills that are needed to keep democracies alive.
(訳) 国家利益を熱望するために、国々やその教育システムは、民主社会を存続させ続けさせるのに必要な技術を、うかうかと捨てている。
次にやっと民主主義の危機の原因を挙げている。
What are these radical changes? The humanities and the arts are being cut away, in both primary/ secondary and college/university education, in virtually every nation of the world.
(訳) このような過激な変化は何であろうか?人文科学や芸術科目が、初等・中等教育や単科大学・総合大学教育から、世界中のほとんどすべての国で、切り捨てられているのである。
このような変化は、人間の未来に悪影響を与えると、筆者は警告している。
We haven't really deliberated about these changes, we have not really chosen them, and yet they increasingly limit our future.
(訳) 実際には、私たちはこれらの変化について、熟慮してこなかった。実際には、私たちはこのような変化を選んでいなかった。それでもその変化は、私たちの将来をますます制限するであろう。
人間関係の紐帯 soul
人文科学や芸術の軽視は、人と人を結び付ける "soul" を育てることができないと、筆者は主張する。筆者の "soul" の定義は、次のようなものである。
What I do insist on, however, is what both Tagore and Alcott meant by this word: the faculties of thought and imagination that make us human and make our relationships rich human relationships, rather than relationships of mere use and manipulation.
(訳) しかしながら、私が言いたいことは、*タゴールや**オールコットが、魂という言葉で表現したものである。魂とは思考と想像力の能力であり、私たちを人とし、単なる利用と操作の関係ではなく、私たちの人間関係を豊かな関係にするものである。
人文科学や芸術科目の切り捨ては、民主主義の根幹である魂を切り捨てるようなものであると、この英文の筆者は訴えている。
内田樹の英語教育の項で触れたように、私が大学教授だったころも、英語偏重で、英語以外の第二外国語削減の風潮があった。私が勤めていた大学の執行部には、特にドイツ語に嫌悪感を持っている人がいた。言語学習は世界解釈の窓であると、私は主張して、第二外国語削減に一貫して反論したが、人文科学や芸術科目削減には、もっと反対しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーー
* タゴール (1861-1941) インドの詩人、1913 年にノーベル文学賞を受賞
** オールコット (1799-1888) 米国の哲学者、社会改良家