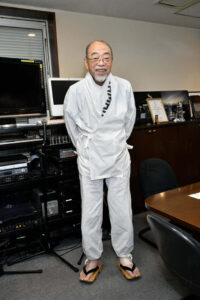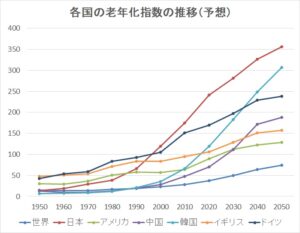サマセット・モームと外国語学習 (Somerset Maugham and Foreign Language Acquisition)
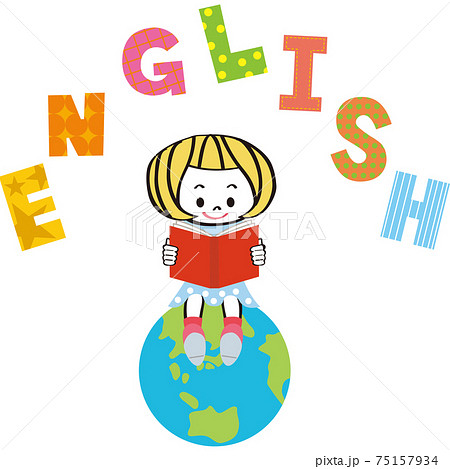
地球に座って英語の勉強 PIXTAより
Somerset Maugham and Foreign Language Acquisition
サマセット・モーム (1874年-1965年)が、晩年に書いたエッセイに『要約すると』(1938年)がある。彼がこの本を書いた年齢が、私と近いせいか、最近この本を読んで、なるほどと思うことがよくある。中村能三『要約すると』(新潮文庫、1968年)と、行方昭夫『サミング・アップ』(岩波文庫、2007年)の二つの翻訳がある。
私自身、大学で長い間(40年間)、英語を教えていたので、彼の外国語学習に対する考え方には、特に興味がある。彼の考えでは、外国語はその国に行って、道を訪ねたり、レストランで料理が注文できるだけでよいことになる。そして “To attempt to learn more is futile” (それ以上、学ぶことは無駄である)と言い切っている。その理由を、長くなるが英文で引用してみよう。
Unless you devote your whole life to it, you will never learn to speak the language of another country to perfection; you will never know its people and its literature with complete intimacy. For they, and the literature which is their expression, are wrought, not only of the actions they perform and the words they use, neither of which offer great difficulty, but of ancestral instincts, shades of feeling that they have absorbed with their mothers’ milk, and innate attitudes which the foreigner can never quite seize. (Somerset Maugham The Summing Up)
少し彼の言い分を聞いてみよう。” Unless you devote your whole life to it, you will never learn to speak the language of another country to perfection” 「一生を外国語学習に費やさない限り、他国の言語を完全に話すことにならないでしょう」と、外国語学習に必要な膨大な時間と努力をあげる。確かに、彼の言葉は真実である。日本人は決してアメリカ人やイギリス人のように、「完全に」英語ができるようにはならないからである。
私がもっとも重要であると思う彼の言葉は、” of ancestral instincts, shades of feeling that they have absorbed with their mothers’ milk”である。訳してみると、「彼らが母乳とともに吸収する、先祖代々の本能や感情のあや」となるが、それらが外国語を学習する人にはない。子供の頃から、その言語の中で育つということは、その言語の雰囲気の中で成長することで、そこには言語の学習以上のものがある。
以前、能役者の子供が、大人になると能役者になることが多いのはどうしてか、不思議に思ったことがある。ある専門家が「能役者の子供は幼少の頃から、能の雰囲気の中で育つから」と、指摘されたことがあった。子供の頃から、親である能役者の所作を見て、言語にはできない能役者の雰囲気を、子供の能役者の身体には染みついている。これが一般人と能役者の大きな違いである。
だから、外国語学習者は常に謙虚になる必要がある。母国語話者が何を感じ、何を考えるかは、私たちは完全には理解できていないことを、思い知るべきである。これを傲慢にすべて理解できると勘違いをすると、大きな誤解を生んでしまう。言語の奥に広大な文化が存在することを常に意識して、外国語を学ぶ必要がある。そのようなことを念頭に置いて、標準的な外国語 (方言まで理解しようと思えば何回も生まれ変わらないとできない) で話される言語を理解し、自分の思想を正しい文法で表現 (正しい文法で話すと母語話者の尊敬を得ることができる) する能力を養うことが肝要である。
東京大学名誉教授のロバート・キャンベル氏は、アメリカ合衆国の出身であるが、日本語や日本文学に、日本人以上に堪能である。しかし「先祖代々の本能や感情のあや」に関しては、それを感じとることが、最初は困難であったことは想像に難くない。むしろその感覚が希薄であったからこそ、日本文学へ新しい切り口を開拓されたのかも知れない。
モームの『要約すると』を読んで、外国語学習について考えてみたが、この問題は思った以上に根が深い。