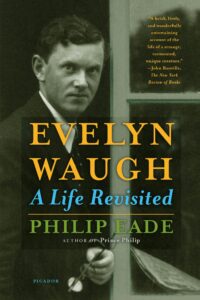イギリスでの研究 (My Research in England)

アレックス・ジェニングス 映画ポップコーンより
このブログの作成者は、2 回イギリスに留学して、シェイクスピア研究に携わった。1 回目は、1978 年で、2 回目は 1997 年であった。その 2 回目の報告のコピーがあったので、ここに転載してみたい。
カレッジと在外研究の目的
今回の留学では、ケンブリッジ大学の聖エドマンド・カレッジに籍を置き、シェイクスピアに関する資料収集と観劇が主な目的であった。ケンブリッジ大学のカレッジの中で、聖エドマンド・カレッジを選んだ理由は、19 年前ケンブリッジに留学した時、お世話になったからであり、またカレッジ構成員が少人数であることも気に入っていた。資料集めによく通った大学図書館から、歩いて 15 分くらいのところにある、こじんまりとしたカレッジは、世間の慌ただしさから完全に隔離された別世界のような趣があった。おまけに 6 月頃から夏休みに入り、学生の姿はほとんど見えず、静かな環境の中でよく散策をしたもので、イギリス生活での良き思い出の一つになっている。10 月に入ると長い夏休みから学生がカレッジに帰ってきて、一挙に活発な雰囲気を取り戻した。
10 月からケンブリッジ大学の英文科で面白そうな講義を聴いてみたが、学部学生が対象のためか既知の講義が多く、あまり知的刺激は受けなかった。しかし教官が時間どおりに来て、かっきり 1 時間、起承転結のはっきりした講義をしていくことには感銘を受けた。ほとんどの教官はペーパーに書いてある文章を読み上げる形式であったが、時間が足りなくなり数ページを飛ばす教官も中にはいた。 最後の授業の時、「講義の評価アンケート」を渡され、学生が教授の授業の評価をしていたのは、19 年前のイギリス留学にはなかった光景であり、新鮮な驚きを受けた。
ロンドンの演劇事情
ロンドンでは、ちょうど私がイギリスに行った時、グローブ座がテムズ河畔に完成し、皮切り公演に「ヘンリー五世」と「冬物語」をしていた。劇はまずまずの出来であったが、グローブ座の中央は天井がなく、雨が降ると観客が濡れていたのが気の毒であった。立ち見席で料金が安いのは大きなメリットであるが、雨に濡れては折角の芝居も楽しめないのではと心配した。
ロンドンにはバービカン・センターという劇場もあり、半年遅れの 10 月から、ストラットフォード・アポン・エイボンで公演していたシェイクスピアの演劇をしていた。私は 6 月頃からストラットフォード・アポン・エイボンで見ていたので、同じ劇を 2 回見たことになるが、「ハムレット」や「スペイン悲劇」などは、何回見ても感銘を受けた。他にリージェント・パークにある野外劇場でも芝居があったが、ここは水準が少し落ちる気がした。しかし自然の木を利用して「真夏の夜の夢」などを演じているのは、興味深く思った。実は 19 年前にイギリスに行った時も、同じ場所で同じ芝居を見たが、その時は丁度花の散る時期と重なり、夢幻の世界で演じられているような印象を受けた。今回もその時の印象を持って臨んだが、時期が違っていたため、花の散る風景には巡り合わなかった。
ウォータールー駅近くに位置するオールド・ヴィック劇場やヤング・ヴィック劇場でも、シェイクスピアの演劇を上演していたが、10 月 29 日にオールド・ヴィックで見た「リア王」は、忠実にテキストに沿った形式で演じられ、退屈しない芝居に仕上がっていた。またヤング・ヴィックで、9 月 18 日に見た「間違いの喜劇」はずっと前に別れた双子の召し使いが、両方とも頭を坊主にして面白い演出であった。
8 月 16 日にはナショナル・シアターで違う演出の「リア王」を見たが、これには強烈な印象を私の脳裏に残した場面がある。主人公リアを演じる役者が、途中丸裸になったことである。体当たりの演技として、新聞批評には高く評価されていたが、私はあまり迫力のある演技とは思われなかった。役者が小さく貧相で、リア王のイメージと合わなかったこともあるが、台詞の言い回しや動作が子供っぽく好きになれなかった。またシェイクスピアの演劇とは直接関係ないが、シェイクスピアの娘スザンナを主人公にした芝居が、コベントガーデンにあるダッチェス劇場に掛かっていたのを見たが、イギリス国民にとって、シェイクスピアの存在が如何に大きいものであるかが実感できた。
ストラットフォード・アポン・エイボン
シェイクスピアの芝居を語るには、ストラットフォード・アポン・エイボンの存在を省くわけにはいかない。ウォーリックシャー州にあるケンブリッジより一回り小さい町であるが、夏には観光客があふれ、活気に満ちた観光地になる。前回のイギリス留学でも訪問したが、その時はまだマークス・アンド・スペンサーもロイド・バンクもなかったが、今では都会的な雰囲気をもつ新しい町に変化していた。7 月 3 日に最初に行ってから数回は通ったであろうか。わざわざ遠くから行くのであるから芝居を 2 本見て帰ることにしていたが、往復 6 時間、芝居見物が約 6 時間で、肉体的にはハードなスケジュールであった。
しかし直接シェイクスピアの芝居に触れる喜びは、全く疲労を感じなかった。最初に見た芝居は「ハムレット」と「シンベリン」であったが、両作品とも思い出深いもので、「ハムレット」は修士論文のテーマであり、「シンベリン」は 19 年前の訪英の時見て、途中で気分が悪くなり劇場から出て悔しい思いをした作品であった。幸い今回は無事最後まで見ることができたが、隣に座っていた英国紳士から感想を求められ、19 年前に半分見たことや、私が英国に来た時は 2 回とも政権交代 (19 年前は労働党から保守党、今回は保守党から労働党)があったことなどを話したら、興味深く聞いてくれた。中学校で英語の教師をしているというその紳士から、どこかでもっと話そうと誘われたが、夜の部の「ハムレット」を見るためには、一度 B & B (宿泊と翌朝の食事を提供してくれるイギリスの民宿) に帰る必要があったので、ロイヤル・シェイクスピア劇場の前で別れた。もっと余裕のあるスケジュールでないと、折角の出会いも潰えてしまうことを実感し残念に思った。
もう一つの作品「ハムレット」については面白いことがあった。前にも書いたように、半年遅れでストラットフォード・アポン・エイボンで掛かっていた芝居が、ロンドンのバービカン・センターでも上演されるので見に行ったら、一幕一場で舞台上の穴が閉じなくなり、一時演技が中断された。シェイクスピアの芝居に足繁く通っている人も、このような経験はあまりないのではなかろうか。劇団の支配人が事情の説明をして、良心的にも最初からの演技を俳優達に指示してくれた。
名優アレックス・ジェニング
次にストラットフォード・アポン・エイボンに行ったのは、その翌週であった。今度は「ウィンザーの陽気な女房達」と「空騒ぎ」で 2 つとも肩が凝らずに楽しめた。ただ興味深いことは、先週見た「ハムレット」で主人公ハムレットを演じた俳優が「空騒ぎ」のクローディオーを演じていたことだ。彼の名前はアレックス・ジェニングと言い、今売り出しの俳優であった。軽妙な演技でハムレットにはあまり似つかわしくないと思われたが、クローディオーは素晴らしい演技で、新聞の批評も概ね好評であった。彼にはヘンリー・ジェイムズの作品を映画化した「鳩の翼」の中でも会った。退廃した雰囲気を持つ英国貴族を、その映画の中で演じており、舞台で見せる姿とは別な面を見せて興味深かった。
アレックス・ジェニングに次に会ったのは、12 月 6 日の土曜日であった。バービカン・センターで「ハムレット」の俳優達と観客とのディスカッションと劇の上演があったので出かけて行った(劇が中断したのはこの時のことである)。台詞の覚え方、役の作り方、化粧や衣装の決定方法、照明の当て方など興味あることが聞けた。ある俳優が折角台詞を覚えて第 1 回目のリハーサルに張り切って出席したところ、監督からその部分は省くと言われてがっかりしたという発言には観客から爆笑が起こった。アレックス・ジェニングは俳優としては断固たる思い切った演技をするが、個人としては控えめで静かな男性のようであまり発言はしなかった。その時ディスカッションの司会をした女性の英語は完璧なもので、外国人の私にも聞きやすく、このような人が英語教師であったらいいなと切実に思った。ただ一緒に行ったイギリス人は、彼女の英語の中にかすかにアイルランド訛りを感じたと言って、私を驚かせた。
「スペイン悲劇」の素晴らしさ
3 回目にストラットフォード・アポン・エイボンに行ったのは、8 月に入ってからである。今回見た芝居は「スペイン悲劇」と「ヘンリー八世」であった。「スペイン悲劇」は、今回の留学で見た劇の内で最高の作品だと思った。主人公のヒエロニモーを演じる中年の少し太った俳優の演技が素晴らしく、作品全体を引き締めていた。作品自体はグロテスクな内容で、本で読んだ時はあまり好きにはなれなかったが、この劇の上演を見て印象が変わった。当たり前のことであるが、劇を読むことと見ることには雲泥の差があるということを実感として感じた。この芝居はバービカン・センターでも見に行き、ディスカッションにも参加したが、いづれも素晴らしいもので、イギリスにいる幸せをかみしめたものである。「ヘンリー八世」も読んだ時は退屈な物語で、人物描写も深みが無いように感じられたが、芝居を見てみると、正に言語だけでなく衣装や雰囲気で観客を魅了する作品であることが了解できた。エリザベス女王の賛美に尽きるこの作品は、ただ読んだだけでは理解不能なものであった。
4 回目のストラットフォード・アポン・エイボン訪問は、9 月 13 日であった。「ヘンリー五世」の芝居が始まったので、是非とも見たいと思ってスケジュールの調整と切符の手配が終わりしだい飛ぶように行った。この芝居は「スペイン悲劇」の次に良かったと思っている。時代背景を第 2 次大戦の頃に設定してあったので多少の違和感があったが、主人公を演じる若い俳優の熱演に観客は酔いしれていた。この芝居に感激して翌週また車をとばして見に行ったが、1 回目より 2 回目の方がより深く鑑賞できた。この留学中に同じ芝居を何回も見たが、2 回目も 3 回目もまったく飽きなかった。それは見るたびに新しい発見があるからである。
前にも書いたが、10月からケンブリッジ大学の授業が始まったので、ストラットフォード・アポン・エイボンにあまり行けなかった。またシェイクスピアに関する資料集めに、ケンブリッジ大学図書館やロンドンの大英図書館に通っていたこともあって、最後にその町を訪れたのは、年も改まった 1 月 31 日であった。今回は「ロミオとジュリエット」と「ベニスの商人」で、人口に膾炙した作品であったが、あまり印象に残っていない。私の体調が悪かったのか、あるいは芝居の出来がお粗末だったのか。おそらく両方であろう。この旅が留学最後の旅になると思うと、つい感傷的になり町の隅から隅まで歩いてみた。その時思ったことは、この町がロンドンやケンブリッジよりも、私としっくり合った町であったことで、いつかまた遠くない将来にここに来て、町を歩いたり芝居を見たりしながら、シェイクスピアに思いを馳せようと誓ったことであった。