内田樹氏の英語教育 (Uchida Tatsuru's English Education)
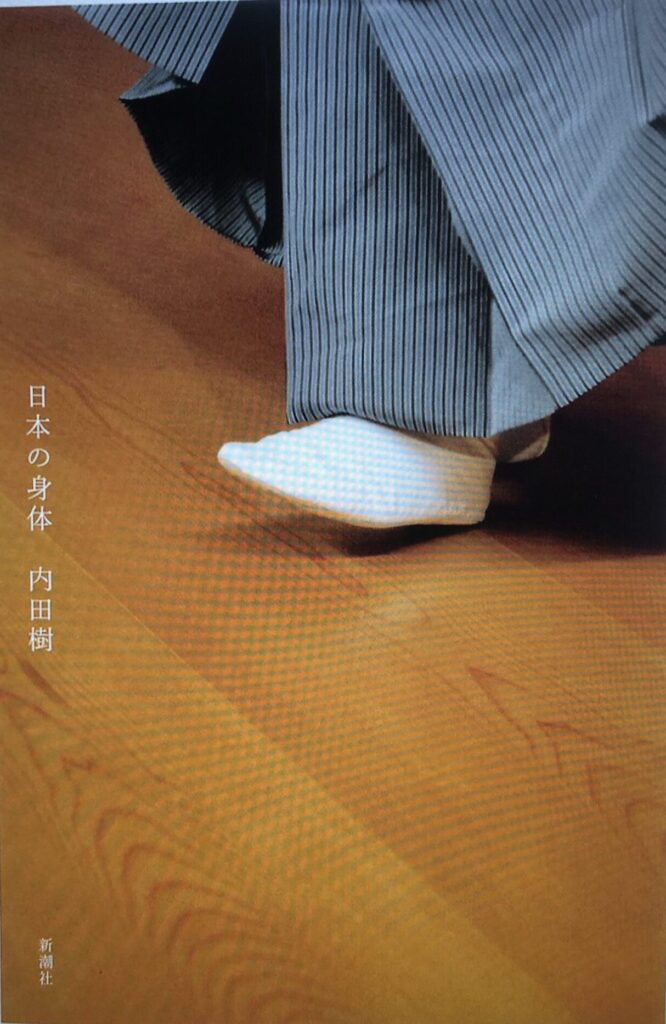
内田樹著 新潮社刊行『日本の身体』
内田樹氏は、日本における現代思想家の代表と目される人であるが、長年、大学教育に携わっておられたので、教育に関する論考・講演も多い。このブログでは「東京私学教育研究所所報」(第84号)に掲載された英語教育についての講演について触れてみたい。2018 年 6 月 12 日に講演された論考を、2019 年春に掲載されたものである。内田樹氏のこの講演は、英語教育者だけではなく、すべての教育者に読んでほしいものである。
講演の歴史的背景を記すと、大学入試問題に民間の英語検定試験を導入しようと、文部科学省が提案をしていたころである。ご承知のように、この試みは受験生の混乱を招くという理由で、正式に却下された。この間の事情は、興味あるものであるが、他の機会に触れてみたいと思う。
外国語教育は武道の指導に通じる
講演の中で、特に、私の注意を引いた箇所は次のような文章である。少し長くなるが引用しよう。
僕は武道を教えていますけれども、それは今の子供たちに、「君たちが自然だと思っている身体運用以外の仕方がある」ということを、教えるためです。身体の使い方は、言語と同じように構造化されています。子供たちが、現代的な言語運用のルールに緊縛されているように、現代的な身体運用のルールに緊縛されて、それが自然だと思って暮らしている。すべての人間は、自分と同じように身体を使って外界を感じ、身体を動かしている、そう素朴に信じきっているわけです。人間の身体は太古から現代まで、世界中どこでも「同じようなもの」だと信じきっている。でも、彼らの身体運用はまさに 2018 年の現代の都市で暮らしている子供たちに、選択的に強制された「奇妙な」身体の使い方なのです。一つの民族誌的奇習なのです。歩き方も、座り方も、表情の作り方も、声の出し方も、全て集団的に規制されている。
それとは違う身体の使い方があることを、例えば、中世や戦国時代の日本人の身体の使い方があることを、僕は武道を通じて教えているわけです。子供たちを、その文化的閉域から解放するために、武道を教えているわけです。君たちは学べば、普段の身体の使い方とは違う身体の使い方ができるようになる。その「別の身体」から見える世界の風景は、彼らがふだん見慣れたものとは全く違ったものになる。それは外国語を学んで、外国語で世界を分節し、外国語で自分の感情や信念を語る経験と、深く通じています。自分には、さまざまな世界をさまざまな仕方で経験する自由があること、それを子供たちは知るべきなのです。
結局、教育に携わる人たちは、どんな教科を教える場合でも、おそらく無意識的にはそういう作業していると思うのです。子供たちが閉じ込められている狭苦しい「檻」、彼らは「これが全世界」だと思い込んでいる閉所から、彼らを外に連れ出し、「世界がもっと広く、多様だ」ということを教えること、これが教育において、最も大切なことだと、僕は思います。
外国語教育は、武道を教えることと同じく、これまで思い込んでいた思考から抜け出す手助けをすることであると、内田樹氏は語る。確かにそうで、英語を学ぶことは日本語の思考枠組みから離れて、より自由に考えることを可能にする。言語は、現実を切り取る道具であるが、日本語には日本語の切り取り方があるし、英語には英語の切り取り方がある。一生の間、一つの切り方しか知らないということは、多様な現実を一面しか見ていないことになる。ある事象を別な角度から見つける能力は、人に広い地平線を約束してくれる。
第二外国語への圧力
大学の教員のときに、大学執行部から第二外国語の削減を厳しく迫られたことがあった。私は英語教員で当時は研究院長の職にあったが、未修外国語を削減することには反対であった。英語だけを習得して、他の外国語を知らないことは、知見の幅を縮小させることに繋がると考えたからだ。特に、ドイツ語に対する攻撃がすさまじかった。私は上記の理論を大学執行部へ何度も話した。会議のあるたびに、私がそのような持論を展開するものだから、おそらく当時の総長は私にうんざりされていたことであろう。しかし私の方針は間違っていなかったと今でも確信している。
私は大学で 40 年間英語教育に関わってきたが、その間、英語読解を中心に教えてきた。もっとコミュニケーションを重視した授業にすればよかったと、時々、後悔することがあるが、この講演を読んだ後は、学生たちの世界を少しは拡大したのではないかと、自分を慰めている。オーラル英語教育は、インターネットを聞けば、いつでも習える。だが英文を正確に理解することは、異次元の世界に参入することを意味する。狭苦しい「檻」から学生を少しでも解放したと思えば、私の教育生活も無駄ではなかったことになる。
(English)
Uchida Tatsuru is regarded as one of the leading contemporary thinkers in Japan, and having been involved in university education for many years, he has produced many essays and lectures on education. In this blog entry, I would like to discuss his lecture on English education published in "the Tokyo Private School Educational Research Institute Bulletin (No. 84)". The lecture was delivered on June 12, 2018, and published in the spring of 2019. Uchida’s talk is something I hope not only English-language educators, but all educators will read.
To describe the historical background of the lecture: at the time, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) was proposing to introduce private-sector English proficiency tests into the university entrance examination system. As you know, this attempt was officially rejected on the grounds that it would cause confusion among students preparing for an entrance examination. The circumstances surrounding this matter are interesting in themselves, but I will address them on another occasion.
Foreign-language education is akin to training in martial arts
In the lecture, the passage that particularly caught my attention is the following. It is a bit long, but let me quote it.
“I teach martial arts, and I do so in order to show today’s children that there are ways of using the body other than what they assume to be natural. The way we use our bodies is structured, just like language. Children are bound by the rules of modern linguistic usage, and in the same way, they are bound by the rules of contemporary bodily usage, living under the assumption that this is natural. People naïvely believe that everyone uses their body to sense and act upon the world in the same way they do. They believe that human bodies, from ancient times to the present and all across the world, are essentially ‘the same.’ But in fact, the way they use their bodies is a ‘peculiar’ mode of bodily usage selectively imposed upon children living in a modern city in 2018. It is a kind of ethnographic custom. Their way of walking, sitting, forming facial expressions, producing their voice—every one of these is collectively regulated.
What I teach through martial arts is that there are other ways of using the body—for example, the bodily practices of people in medieval or Sengoku-era Japan. I teach martial arts to free children from that culturally enclosed space. When they learn, they acquire ways of using their bodies different from their usual habits. And the landscape of the world seen from that ‘other body’ becomes completely different from what they are accustomed to seeing. This is deeply connected to the experience of learning a foreign language, articulating the world through that language, and expressing one’s emotions and convictions in it. Children need to know that they have the freedom to experience the world in multiple ways.
In the end, I believe that people engaged in education, whatever subject they teach, are probably—albeit unconsciously—engaged in this very task. The most important thing in education is to lead children out of the cramped ‘cage’ in which they are confined, the small space they believe to be ‘the whole world,’ and to show them that the world is much broader and more diverse.”
Uchida argues that foreign-language education, like the teaching of martial arts, helps learners break free from the patterns of thought they have taken for granted. Indeed, learning English enables one to step outside the cognitive framework of the Japanese language and to think more freely. Language is a tool for carving up reality, but Japanese has its own way of carving reality, and English has its own. If one knows only a single mode of interpretation throughout one’s life, one ends up seeing only one side of the multifaceted reality around us. The ability to view a phenomenon from a different angle promises a broader horizon for any individual.
The Pressure on A Second Foreign Language
When I was a university faculty member, there was a time when the university administration strongly pressed us to cut second foreign language courses. I was an English professor and was serving as the dean of the research institute at the time, but I opposed the reduction of unacquired foreign language requirements. This was because I believed that learning only English while knowing no other foreign languages would inevitably lead to a narrowing of one’s intellectual horizons. The attacks on German in particular were relentless. I repeatedly explained the above reasoning to the university administration. Since I would bring up this view every time we had a meeting, the university president at the time was probably fed up with me. Yet even now, I am convinced that my position was not mistaken.
I was involved in English education at the university for 40 years, during which I mainly taught English reading. I sometimes regret that I did not place greater emphasis on communication-oriented instruction, but after reading this lecture, I comfort myself by thinking that I may have at least broadened my students’ world a little. Oral English education can be learned anytime by listening on the internet. But accurately understanding written English means entering a different dimension. If I was able to free my students even slightly from the narrow “cage” they were confined in, then my life as an educator was not in vain.


